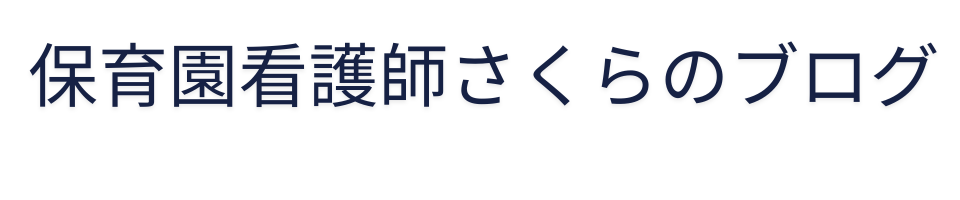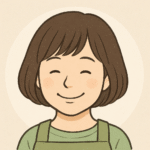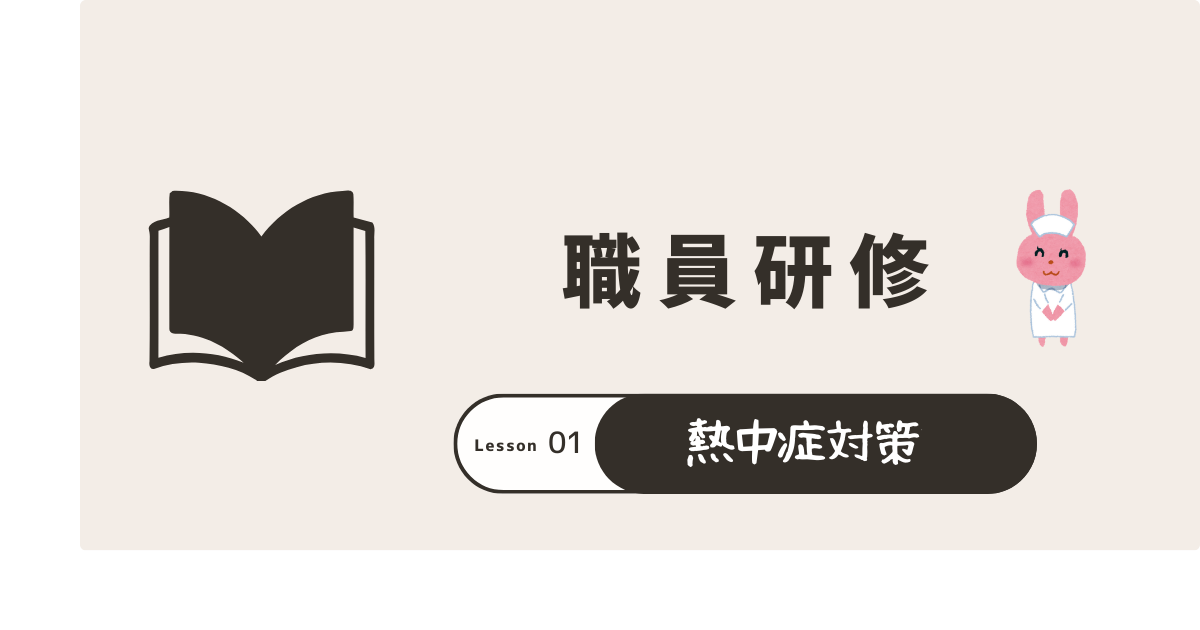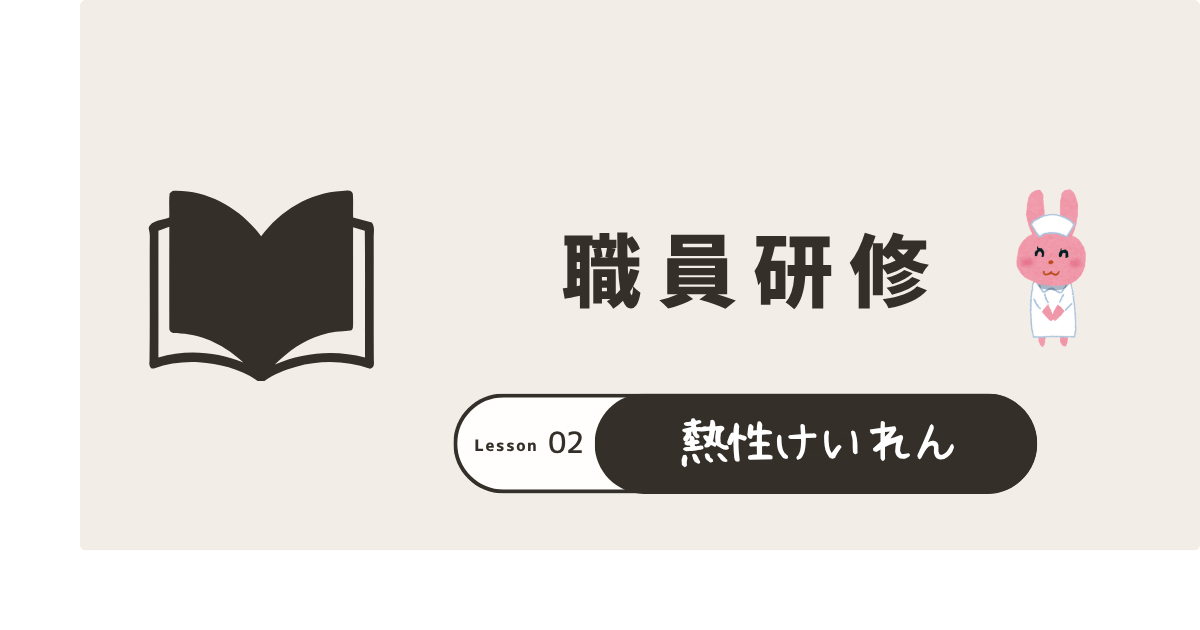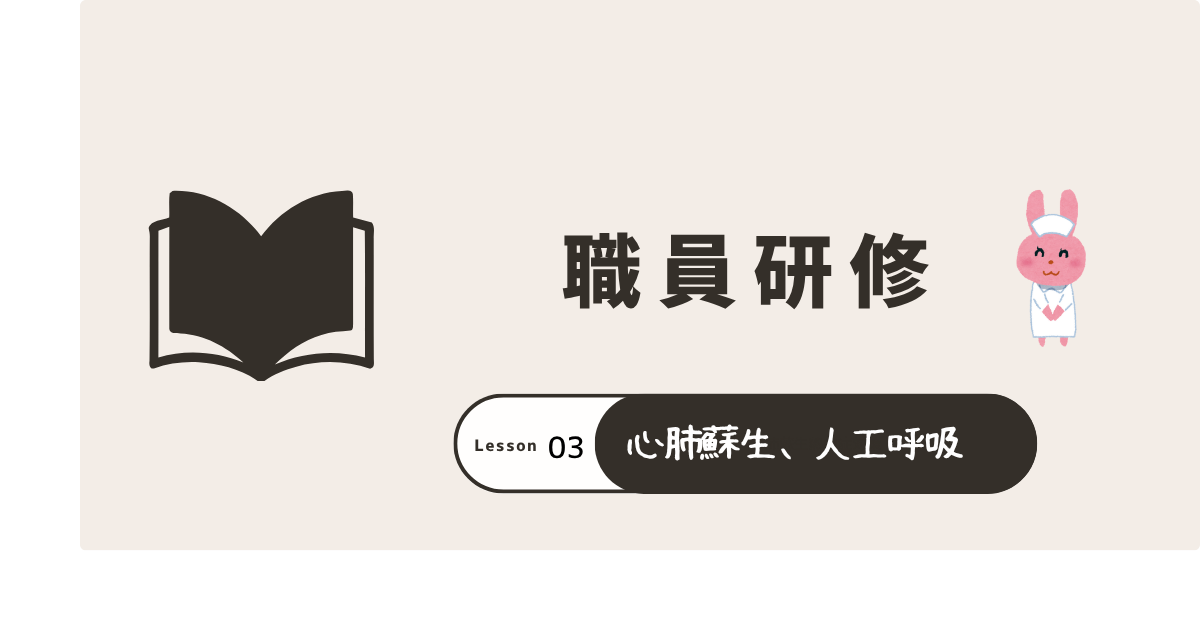保育園園内研修 食事の介助について
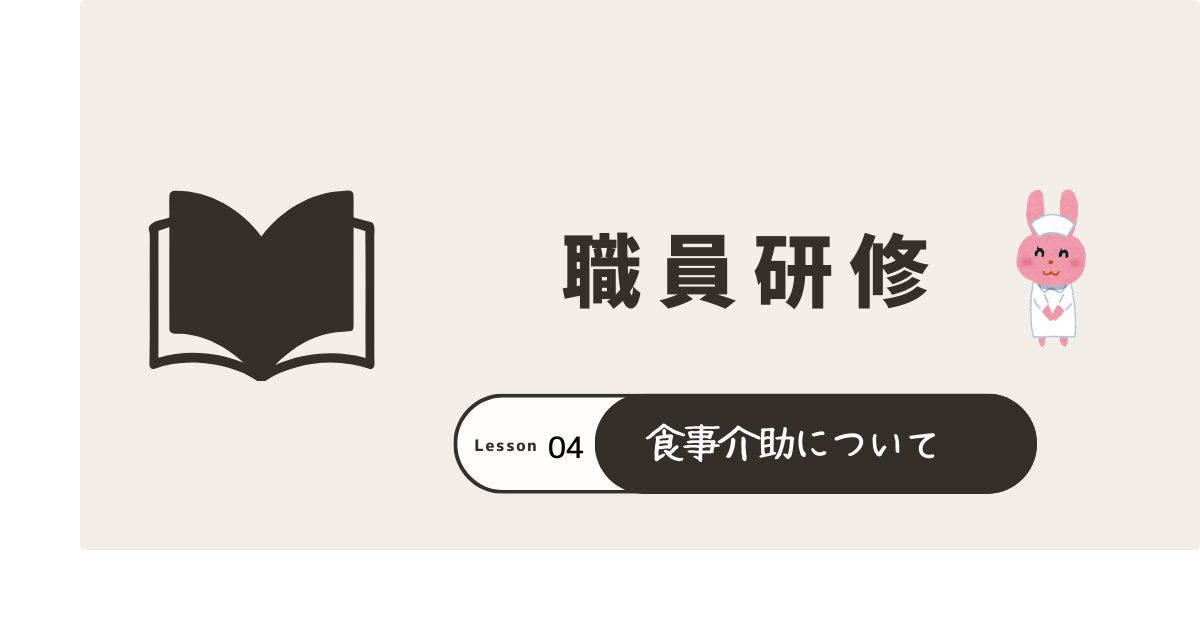
こんにちは。保育園看護師さくらのブログをご覧いただきありがとうございます。
このブログでは、保育園看護師のお仕事について、また子どもの病気のことなど子どもに関わる方に向けてお話させていただきたいと思っております。
今回は保育園の職員に向けた研修で「食事介助について」考えてみました。
離乳食の時の介助がのちのちの子どもの成長にも大きく影響するというのは過言ではありません。丸のみ、口にため込む、遊び食べなどの色々な問題もあります。
先生たちは子ども個人を見ながら、その子に合った介助をしていると思いますが、今回は研修なので一般的な「食事の介助」ということの内容です。
離乳食初期は「つぶす練習」
離乳食中期は「つぶす練習」
離乳食後期は「かじる練習」
幼児食前期は「食事の形を整える」
幼児食後期は「大人と同じリズムで食べる」
を目標に私たちがどういう介助をしていけばいいか、また注意点など記していけたらいいなと思います。
離乳食初期(歯の萌出なし、生後6か月前後)の食事の介助のしかた

・ 食べ物の形状:ドロドロ状(ポタージュ)
【成人嚥下獲得期】と言われる時期です。
哺乳だけする口の動きから舌が前後に動くようになり、食べ物を口にためて、舌で喉の奥に送りこめるようになります。(ただし、飲み込む時に下唇が内側にめくれこむことが多い。口角はあまり動かない。顎の動きがみられるようになる。)
*食事支援のポイント
・指しゃぶり、手しゃぶりによる手と口の協調を促進します。
生後2~3か月からさかんになる指しゃぶり、手しゃぶりは最初は哺乳の反射の延長にあるが、自分から手や指を口に持っていってなめしゃぶるうちに、徐々に手と口の協調動作が育つため、止めることはせず十分させる。
・「口遊び」のサポートをする(哺乳反射の減弱と口の随意的な動きの促進)
指しゃぶりに続いて、生後4か月ごろからおもちゃや身の回りの物をしゃぶる行為が見られます。色々な形や硬さのものを口に取り込み、しゃぶって舌や顎を動かすことで哺乳の反射は減弱し、口の随意的な動きが発達します。口に入れても安全なおもちゃを与え、十分に口遊びをさせてあげることが大切ですね。
・口の中を観察します。
授乳期の乳児の口の中は、哺乳に適した形態をしています。中央が凹んだ上顎、歯の生えていない歯槽弓、脂肪でふっくらした頬部など、舌を使って効率よく哺乳するのに最適な形をしています。しかし、生後半年の間に下顎は著しく成長し、高さも増して、上下の顎の位置関係も変化します。これらは離乳期になって、唇を閉じたり、舌が口の中におさまって食べ物を処理する動きを獲得するための準備となっています。
★介助のしかた
平スプーンを下唇にのせ上唇が閉じるのを待ちます。唇で食べ物を取り込むようにすると、口を閉じる力が鍛えられます。
★介助の注意点
食品の大きさ・形状・温度(40度前後)・量・粘着度・一口量は適切か
食べ物をしっかり飲み込んだことを確認しながら介助を行います。
「ごっくん」と声掛けします。
食事中、眠くなっていないか注意する。
離乳期中期(前歯が生え始める。7~8か月)の食事介助について

・食べ物の形状:舌でつぶせる硬さ。つぶしたものをひとまとめにする動きを覚え始める時期。
【押しつぶし機能獲得期】舌を上顎に押し付け、豆腐くらいの硬さをつぶすことができるようになります。(舌の前後に上下運動が加わる。数回もぐもぐした後、顎が止まり、上下の唇がしっかり閉じる。左右の口角が強く引けることにより、上下の唇が薄く見える)
※液体の食べ物から固形の食べ物に移行していきます。子どもは哺乳時の「吸う」から「噛む」動きの基礎を学習していきます。
*食育支援のポイント
・口の動きの発達に合わせた離乳の進め方
少し形のある食べ物を舌と上顎でつぶしていく動きを覚えていきます。歯が生えて、口が閉じやすくなり、舌が口の中で動きやすくなると、舌でつぶせない硬さの食べ物をわきの歯ぐきに移動して、上下の歯ぐきでつぶすことを覚えます。これらの動きを引き出すためには、それぞれの時期に合わせた離乳食の調理形態の工夫が必要です。また、歯の生え方が遅い子どもには離乳食の進め方もゆるやかにしていきます。
★介助のしかた
平スプーンを下唇にのせ上唇が閉じるのを待ちます。
舌でつぶせないものは、丸のみしてしまうため硬さや形状に気を付けます
「もぐもぐ、ごっくん」など声掛けします。
足の裏が床や台について姿勢が安定するように座らせます。
離乳期後期(前歯は上下生える。9~11か月の食事介助について

・食べ物の形状:歯ぐきでつぶせる硬さ
【すりつぶし機能獲得】舌が前後、上下の他、左右の動きがでて、指でつぶせる硬さの食物を唾液と混ぜ合わせ、唇を閉じたまま顎を上下に動かせ歯ぐきですりつぶすことができます。
【自食準備期】手と口の協調運動や歯を使う練習などを通して自分で食べる準備をします。
3回の食事で必要な栄養をほぼとれるようになっていく。また歯を使って噛むことを覚えます。乳歯の生え方に応じて「歯を使った咀嚼の動き」を練習しながら、奥歯で噛めるようになれば離乳食は完了し、幼児食に移行します。
*食育支援のポイント
・上下の前が生えたら「かじりとり」の練習を支援します。
上下の前歯が生えそろったら、手づかみで食べ物を口にもってきて、前歯で一口量を調節してかじりとることを覚えます。色々な大きさや形の食べ物を用意して、食材にあわせたかじりとりの経験をさせます。
・「おもちゃ噛み」で力加減を覚えます。
前歯が上下生えてくると、歯ぎしりやおもちゃ噛みが見られやすくなります。これは、自分の歯をどう使うか、どの位の力を入れて噛めばいいかを試している行為と考えれられるため十分行わせることが大切です。
・最初の奥歯で「噛みつぶし」の練習を支援します。
1歳3.4か月のころには最初の奥歯「第一乳臼歯」が生えて、1歳半ごろには上下の奥歯を使って嚙みつぶすことを覚えます。色々な食材を経験しながら、噛み方を練習します。また硬さのある食材はうまく噛めないため、噛みつぶす程度でまとまりやすい食材で咀嚼の発達を支援します。
★介助のしかた
指でつぶせるやわらかさで、形のある食物を介助者が手で持って、前歯を使ってかじり取らせかみ切らせる経験をさせます。
丸み(くぼみ)のあるスプーンを下唇の上にのせ、上唇がとじるのを待つ。歯ぐきでつぶせないものは丸のみしてしまうため注意します。
足の裏が床や台について姿勢が安定するように座らせます。
幼児食前半(~2歳ごろ)の食事介助について

【自食準備期】手や腕の未熟さを補うようにして顔や口の動きを合わせ、自食に向けての機能を獲得する時期です。顔を動かさずに食物を唇の中央でとらえることが出来るようになります。
【食具食べ機能獲得期】
幼児食前半には、食具の使い方を覚えていきます。最初は介助されながら使い、だんだん自分で操作することができるようになっていきます。この時期は基本的な生活習慣が確立されていく時期です。
※離乳食完了のころには、乳児の切歯や第一臼歯は生えてきますが、まだ歯を使った咀嚼機能は十分発達していません。第一乳臼歯は噛む面が小さく、噛む力も弱いため、離乳が完了したからといって、大人と同じ食はとりにくく、乳歯列咬合が完成する3歳ごろまでは、「幼児食」という考え方で食材や調理形態に工夫が必要です。離乳食のままの形態では咀嚼力は伸びないですが、急に固いものや繊維の多い物を与えると、うまく噛めないため「丸のみ」や「ためる」などの食べ方の問題を生じやすくなります。歯の生え方には個人差があるため、生え具合をみながら進めていきます。
好き嫌い、遊び食べなどの食事の問題も多くなっていきます。
*食育支援のポイント
・乳歯の生え方に応じた食材、調理方法の工夫
上下に第一乳臼歯がかみ合うようになりそれほど硬くない食品は噛みつぶして食べられるようになります。少し形の大きい食べ物を前歯でかじりとり、奥歯でかみつぶして食べながら、食べ物の大きさ、硬さに応じた咀嚼の力や回数を覚えていく時期です。この時期の子どもには難しい食材を控えながら、色々な食べ物を経験させていくことで咀嚼力を育てていきます。
・噛みにくい食材には注意が必要です。(窒息事故にも注意)
第一乳臼歯だけではすりつぶしまではできないため、処理できる食べ物には限界があります。繊維の多い物(ゴボウ、きのこ、海藻など)や弾力の強い物(イカ、タコ、白玉、こんにゃくなど)、葉物の野菜など。また、丸くて滑りやすい物(ミニトマト、ぶどうなど)や噛み砕きにくい物(りんご、なしなど)の食材は控えるまたは小さく切ったり、すりおろして与える必要があります。
・子どもの口の中の観察と仕上げ磨き
乳歯が生えてくる本数で、与える食べ物も工夫していく必要があるため、歯の生え具合を把握することもかねて、日ごろから子どもの口の中をよく観察することが重要です。奥歯が生えてくると食後のブラッシングの必要性も高まるため、仕上げ磨きをしながら乳歯の生え方をチェックします。
・「手づかみ食べ」から「食具の使用」へ
「手づかみ食べ」で学習した手と口の協調動作をもとに、スプーンやフォークを持たせて、最初は介助しながら食べ物をすくったり、さしたり、口に持っていくことを覚えさせます。椅子やテーブルの高さを個々に調節して食事時には子どもが食べやすい姿勢を保ちます。
・機能性のある食習慣から食欲を育てる。
3回の食事を中心にした食事になっても、就寝が遅かったり睡眠時間が不規則であると、食事時間も不規則になりがちになります。また、外遊びが少なく、身体を使った遊びが少ないとエネルギーの発散がなく食欲もわかず、おやつや飲み物中心になることもあるため、生活リズムを整え、食べる意欲を育てることは食体験を広げ、咀嚼を発達させるためにも大切です。
・「供食」の大切さ(家族や友だちと共に囲む食卓)
家族や友だちと一緒に食事することから子どもの機能面だけではなく、精神面でも様々なことを学びます。同じものを食べた時に「おいしいね」と共感したり、食べ方をみせて教えていくことも大切です。
・口の機能
柔らくて形の大きな食べ物を唇でとらえて、前歯で一口量を噛みきり、舌で奥歯へ運んでかみつぶし、舌を上顎に追い上げながら集めて飲み込む。噛んでいる時も飲み込んでいる時も唇を閉じていることが大切です。
★食べ方を育てるポイント
・目・手・口の協調運動を覚える。まず、手づかみ食べを十分に行わせて、一口量を覚えます。
・食具の使用:1歳を過ぎると、指先の動きも発達してきて、小さい物をつまんだりすることが上手になってきます。手づかみ食べが上手になってきたらスプーンやフオークを持って食べる練習をします。
・食事中、足をそろえ椅子に深く座り、背中を伸ばして机の方を向き、姿勢をよくして食べられるよう環境を整えたり、指導したりします。
幼児食後半(~3歳ごろ)の食事介助について
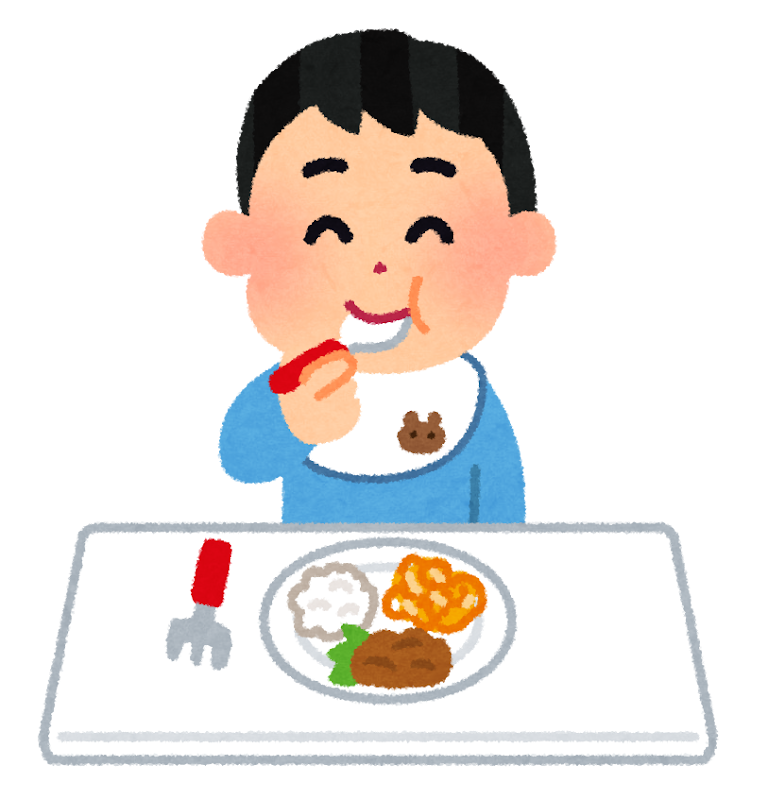
【食具食べ機能獲得期】
摂食機能がほぼ完成し、上手になります。
①唇と前歯で上手に食べ物を取り込むことができるようになります。
②奥歯で食べ物を噛むことができるようになります。
③自分で食器、食具を使用して食べれるようになります。
★成人嚥下が2歳以降も獲得していない場合は医療機関に相談することを検討しましょう。
一番奥の第二乳臼歯が生えてくると、すりつぶしもできるようになるため、ほとんどの食品を処理することができるようになります。食べられる食材の幅がひろがり、咀嚼力も増すため、噛み応えのある食品で咀嚼機能の充実を図ります。
*食育支援のポイント
・噛み応えのある食品で咀嚼力を育てます(食材に応じた噛み方を覚えます)
第二乳臼歯が嚙み合ってくると、すりつぶしが可能になるため、繊維の多いものや硬いもの、弾力のあるものなども食べられるようになります。ただ噛み応えのある物ばかりだと疲れてしまい、途中で食欲を失ったり、食欲がない時食べる気力がなくなったりするため、噛み応えのある食品を適度に取り入れ、食材に応じた噛み方を育てていきます。
・生活リズムを整え、食欲を育てます
睡眠や運動(遊び)の状況は食事のリズムに影響が大きいです。早寝早起きの週間や外遊びのできる環境づくりで生活リズムを整え、間食(甘いお菓子やスナック菓子)や甘味飲料を控えることで、お腹を空かせて食事をとる習慣をつけます。おいしく食べることは食べる意欲を高めるとともに咀嚼機能の発達を促すことにもなります。
・口を閉じてよく噛むことで唾液の分泌を促します。
硬い食べ物や乾燥した物はそのままではうまく飲み込めないです。よく噛んで細かくするとともに唾液と混ぜ合わせることで飲みやすい形になります。咀嚼刺激は唾液の分泌を促すため、口を閉じてよく噛んで食べることは色々な食品をたべられるためにも、味覚を感じやすくおいしく食べるためにも大切です。
・食具の握り方:手掌握りから3指握り(下手持ち)に変えていきます。
体の使い方や遊びから「噛む力」を育てよう

「噛む力」は食べ物を工夫することや食べさせ方を工夫するだけではなく、体の使い方や遊びを通じて体幹や顎や口周りの筋肉がしっかり発達することでついていきます。
腹ばい:首や背中、お腹の筋肉を育てたり、頭を支える力がつきます。
ハイハイ、ずりばい:肩やお腹の筋肉が鍛えられます。
つかまり立ち、伝い歩き:バランス感覚や下半身の筋力を養います。
ぶらさがり遊び:体幹や顎周りが連動して鍛えられます。
ジャンプやかけっこ:全身の安定(食事姿勢の安定)
シャボン玉遊び:息を吐く力、口をすぼめる力がつきます。
他にも自然に笑顔で遊んでいることで全身のありとあらゆる筋肉を鍛えることができます。
まとめ
子どもの食事介助のポイントとして
1,子どもの歯の萌出状態を見極める
歯の生え具合をみて、食材の硬さや形状を決めましょう。個人差を優先し食材を決定します。
2、スプーンの入れ方
スプーンは赤ちゃんの口の奥まで入れないで、唇で食べ物を取り込むようにすると、口を閉じる力が鍛えられます。
3,姿勢を整える
足がぶらぶらしていると体幹が安定せず、噛む力も弱くなります。足の裏が床や台につくようにしてあげましょう。
4,一口の量を少なめに
口いっぱいに入れると丸のみしてしまいます。小さめの一口で「噛む余裕」を作ることが大事です。
5,「ごっくん」「かみかみしよう」などと声をかける
言葉にして伝えることで、子どもは自分の動きを意識できます。
6,家族と一緒に食べる
子どもは大人の食べ方をよく見ています。大人が「もぐもぐ」と噛んでおいしそうに食べている所を見せると、自然と真似をします。
さらに、運動や遊びで「噛む力をアップ」
・たくさん全身を使った遊びをしましょう。トンネル遊びやハイハイ競争、お散歩、追いかけっこ、鉄棒のぶら下がり、ジャンプ、かけっこ。シャボン玉、風船などをすると、体幹が鍛えられ姿勢が安定したり、口周りの筋肉や首肩腰の筋肉がつき「噛むための筋肉」が鍛えられます。
そして、たくさん体を動かしたり、楽しむことで「お腹もすきます」
食べることが好き、食べることに興味がある子がたくさん増えるといいなと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございます。少しでも参考になる所があったら幸いです。