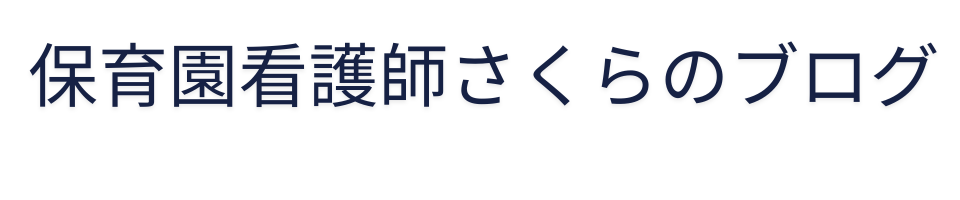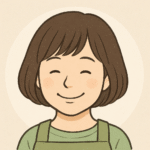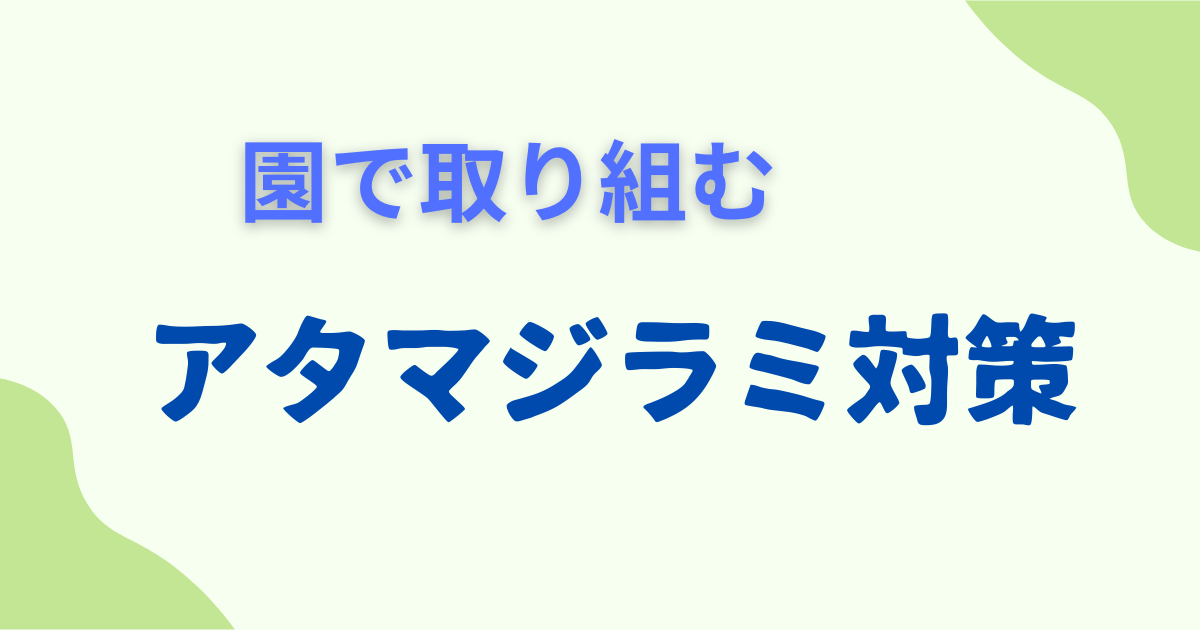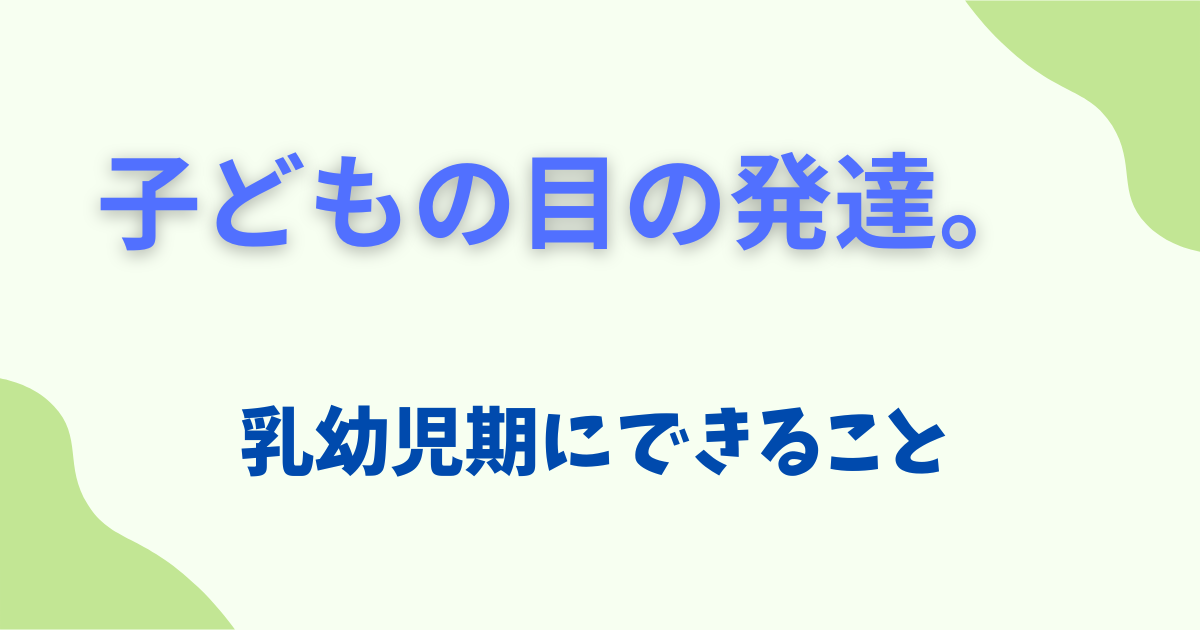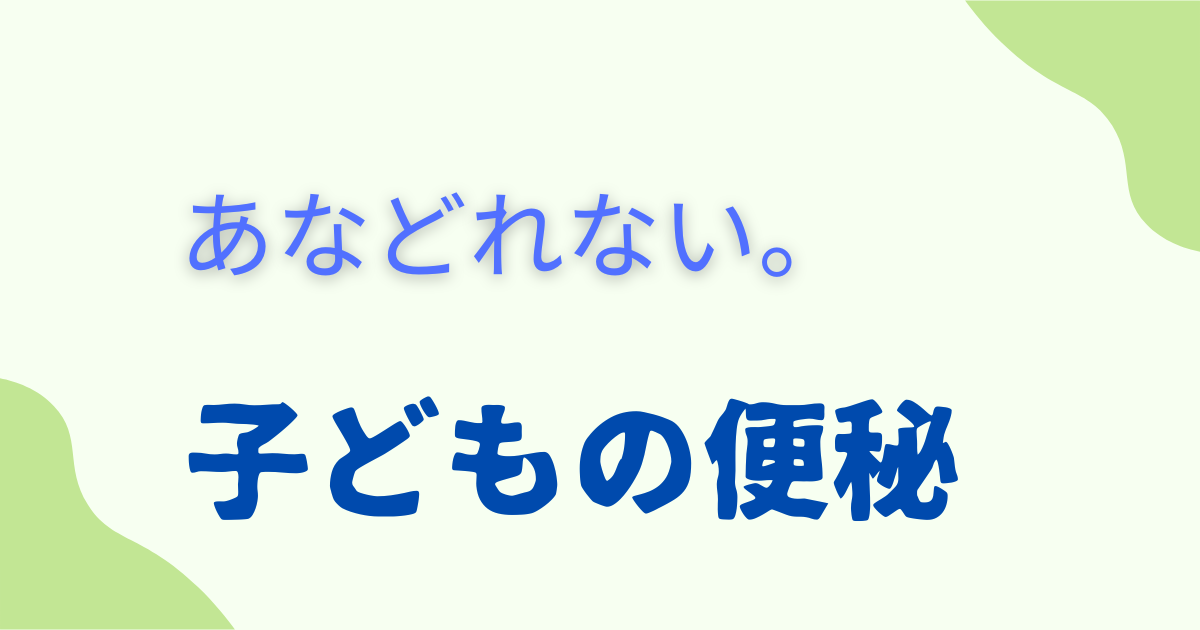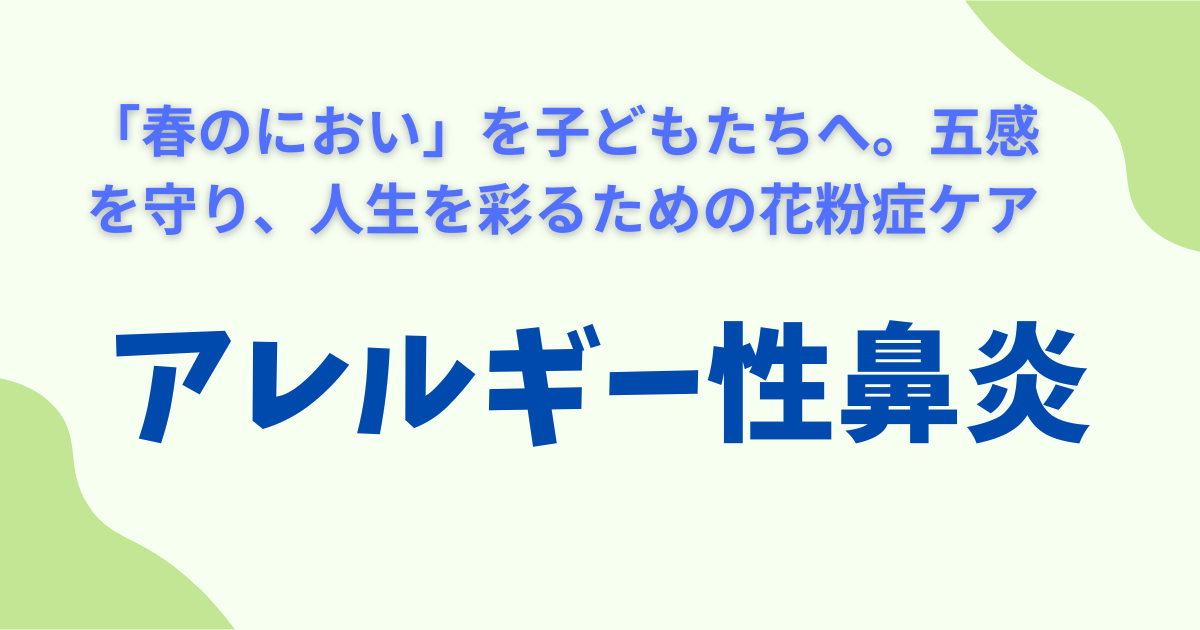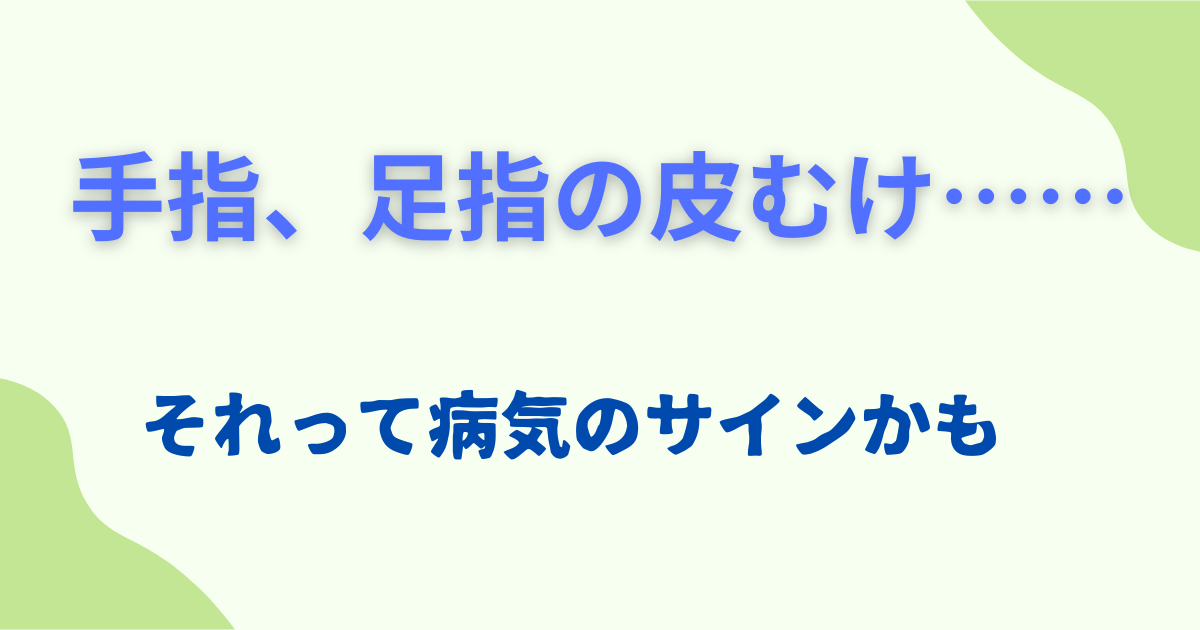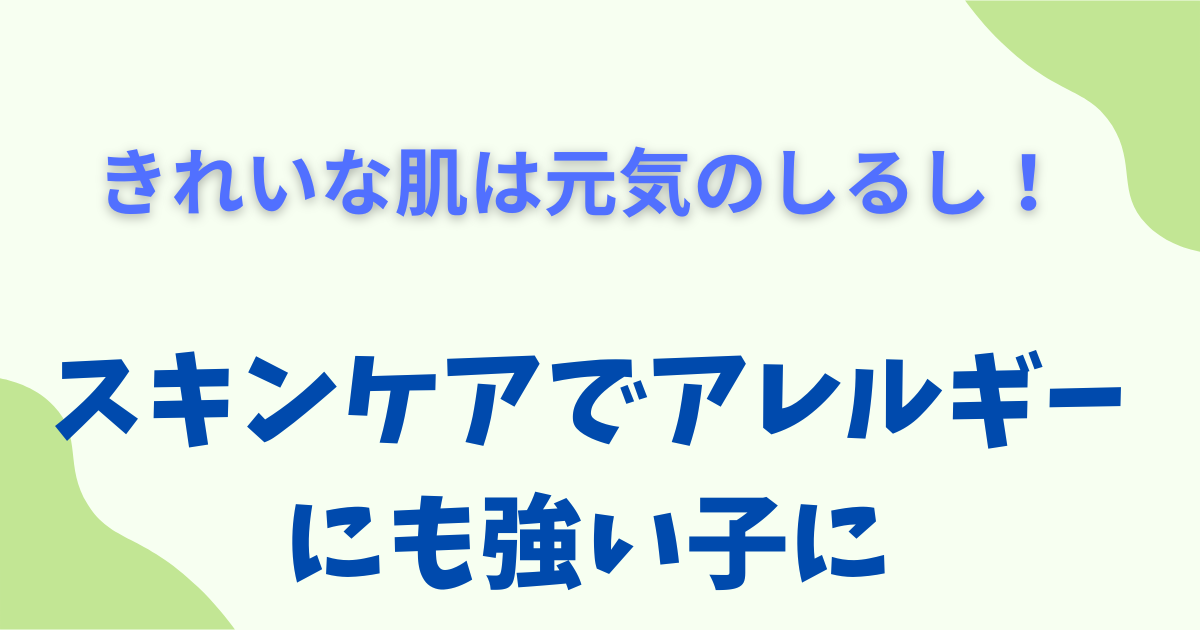心も体も元気いっぱい。子どもの腸活のすすめ
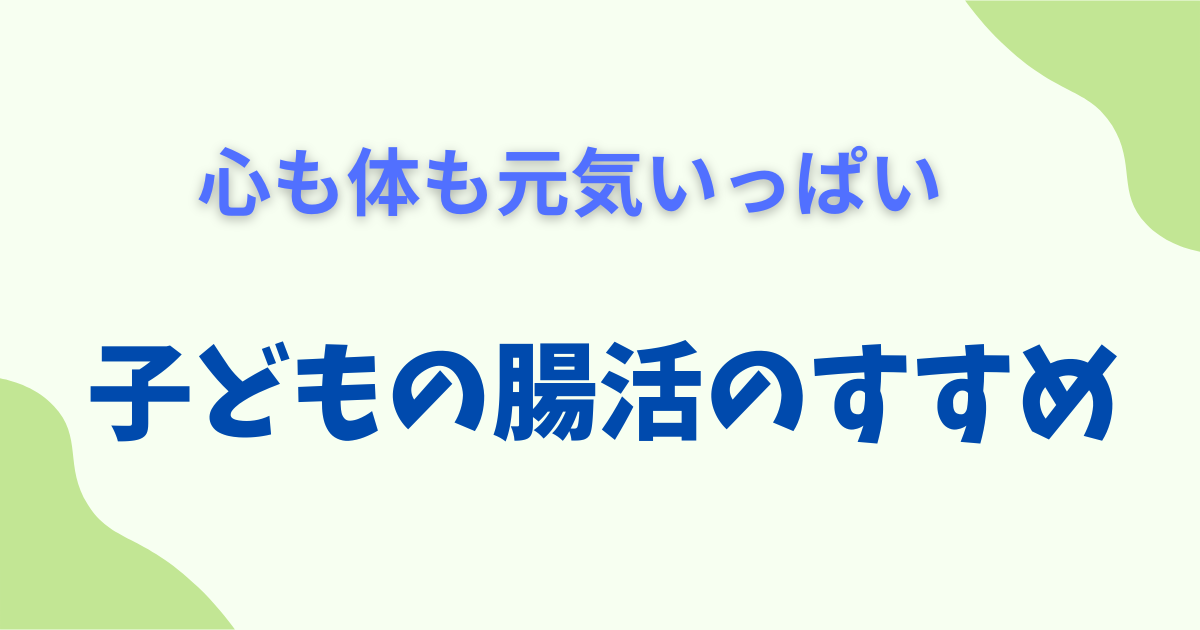
世は「腸活」「腸内フローラ」、「プロバイオティクス」やら「腸内環境をよくしましょう!」とたくさんの本やメディアで情報があふれかえっています。
「腸活」は健康にとっても良いということは知っていても、実際はどういう効果があるのか
子どもの「腸活」ってどういうことをすればいいのか、私なりに調べたことをまとめてみました。
子どもの腸活、いいことたくさん。
よく話題になる腸内フローラ。腸内フローラ(腸内細菌叢)とは腸内に生息する膨大な数の細菌の集まりのことです。
この腸内フローラの細菌の種類を増やし、善玉菌:悪玉菌:日和見菌を2:1:7の割合に整えるのが子どもの腸活も目標になります。
このように腸内フローラが整うと…。
病気になりにくくなる
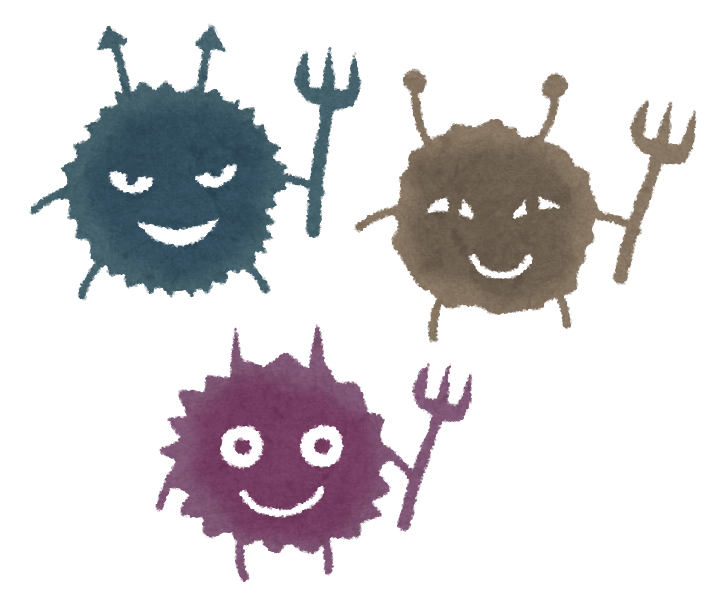
腸と免疫の関係がわかってきていて、腸には「全身の免疫をつかさどる」という重要な役割を担っています。それは体の中の免疫細胞のおよそ7割が腸に集結しているからです。
そして、その役割を果たすうえで、腸内細菌が大活躍しています。
●病原菌(敵)が体に入ってきて、敵を攻撃するまで。
腸に敵が侵入する➡腸管壁になる「バイエル版」がその一部を取り込み、敵の情報を読み解く➡敵の抗体をつくる➡その抗体を使った免疫細胞たちが敵の体内侵入を防ぎます
この時、腸内細菌は腸管の粘膜の分泌を促すとともに自ら腸壁を厚く覆って、敵が入り込むのをブロック。さらに入ってきた敵を免疫細胞が攻撃するという連携プレーで体が病気にならないように守ってくれています。
また、腸内細菌には免疫細胞が攻撃しすぎるのを抑える役割をもつ物もいて、両者がともに働くことで正常な防衛活動を行っています。

この抑える役がいないと、免疫細胞は暴走して攻撃しなくてもよい相手まで攻撃してしまい、その結果、アレルギーや自己免疫疾患を引き起こしてしまうんですって。
アレルギーや自己免疫疾患を抑える免疫細胞が「Tレグ」と言って、腸内細菌によって作り出されたものです。
ご機嫌でいられる

幸せホルモンと呼ばれている「セロトニン」は腸で9割作られているそうです。
「セロトニン」は気分を安定させ穏やかにしたり、頭の回転をよくして直観力を高めたりします。
セロトニンは、食物中から摂取されたトリプトファンというアミノ酸をもとに合成されるのですが、この合成にはビタミンB6・ナイアシ・葉酸などのビタミンが必要で、これらのビタミンは腸内細菌が合成しているのです。
また、腸内細菌は快楽ホルモンと言われる「ドーパミン」の合成にも関わっています。
「ドーパミン」はやる気を高め、楽しくポジティブな気持ちにさせる働きがあります。
人は、セロトニンが不足すると精神が不安定になっておこりっぱくなり、ドーパミンが不足するとやる気を失って無気力になります。
うつ病はセロトニンやドーパミンが不足すると引き起こされると言われています。また、近年「自閉症」や「引きこもり」なども腸内細菌が深く関係しているのではないかと研究されています。
腸内環境をよくすることで、セロトニンやドーパミンを増やした子どもたちが常に「ポジティブな気持ち」でいられるといいですね。
子どもの腸活、どうすればいいの?
腸内細菌は200種類以上、100兆個以上いると言われています。
そして腸内フローラは菌の数は年齢によって増減するものの、菌の種類は一生を通じてほとんど変わらないそうです。
そして、腸内フローラは生後1歳半ほどで9割ほど決まってしまい、3歳くらいで完成してしまうと言われています。
そして、腸内フローラは多種多様性が大事ということです。人間社会と同じですね😄
しかし、3歳を過ぎてしまったと、あきらめることはありません。
3歳を過ぎてしまうと、種類は増えることはありませんが、良い食生活や良い習慣を送っていけば、細菌の数は増やせることができます。そして今いる善玉菌が優位になるのを助けてくれます。
人や自然と接する機会をたくさん持ちましょう。

無菌状態で生まれた赤ちゃんはお母さんの産道を通るときに、最初にお母さんの菌を受け取ります。そして、そこにいるお医者さんや助産師さん、看護師さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんからも菌を受け取っていきます。帝王切開のお母さんも心配しないでください。赤ちゃんは抱っこされることによって、その人の皮膚常在菌を受け取り、腸内フローラの形成をスタートさせていきますよ。
そのようにしていろんな人と接しながら様々な菌を受け取っていくことが大切です。
また、ペットと触れ合ったり、動物園に行ったり、公園で土と触れ合うこともたくさんしてあげると良いみたいです。
「赤ちゃんはなんでもなめます」なめるからと必要以上に除菌することは、赤ちゃんが菌を獲得することを妨いでしまいます。
反対に赤ちゃんは菌を獲得するために、色々な物をなめているとも言われています。
コロナ以降私たちは、除菌ということを過度に意識して行っていますが、子どもの成長にとっては、適度に手抜きをしておおらかに生活することが「腸」にはいいみたいですよ。
腸がよろこぶものを食べましょう。

腸内細菌のえさになる野菜、豆類、穀類、海藻、発酵食品を積極的にとりましょう。
なかでも最近は食物繊維が大好物です。食物繊維には水溶性と不溶性があり両方しっかりとることが大切です。
水溶性食物繊維:大麦、昆布、わかめ、ひじき、さといも、りんご、キウイ、オートミールなどに多くふくまれています。大腸でビフィズス菌などの善玉菌のえさになり、短鎖脂肪酸をつくります。
不溶性食物繊維:玄米、きゃべつ、レタス、さつまいも、しいたけ、ブロッコリー、大豆などに多く含まれています。便の量を増やしたり、腸を刺激して蠕動運動を促したりします。
発酵食品:納豆、ヨーグルト、ぬか漬け、味噌、チーズなど。発酵食品には発酵にかかわった善玉菌が含まれています。生きたまま腸に届けば腸内フローラの一部になりますし、死んでしまっても、善玉菌のえさとして活用されます。
オリゴ糖:ゴボウ、たまねぎ、とうもろこし、長ネギ、大豆、バナナなど。ビフィズス菌などのえさになって善玉菌を増やす効果があります。
キノコ類:しいたけ、しめじ、なめこなど。水溶性食物繊維の一種であるβ‐グルカンが豊富に含まれていて、免疫力を活性化し、アレルギーを抑制します。
昔、母親から「キノコを食べるとがんにならないよ」とたくさん食べさせられました😓ふと、そんなことを思い出しました💦
オメガ3脂肪酸:アマニ油、青魚など。腸の中の炎症を抑え、善玉菌が増えやすい腸内環境に整えてくれます。体の中では合成できないため、食事からとる必要があります。
たっぷり睡眠をとりましょう。

私たちの体の自律神経は、交感神経と副交感神経という正反対の働きをする2つの神経から成り立っています。昼間は交感神経が優位になって活動しやすくなり、夜は副交感神経が優位になって体を休ませるモードになり、健康を保っています。
腸が主に働くのは、副交感神経が優位になる夜と言われています。
私たちが寝ている間、胃と小腸には蠕動運動とは別の「空腹期収縮運動」が起こり、食べ物や残りかすなどを大腸の奥に運び、胃腸をきれいにします。大腸に運ばれた残りかすは、腸内細菌たちの働きによって、分解されうんちになります。
しっかり睡眠をとることはうんちをつくることにとっても大切なんですね。
外でたくさん遊びましょう。

土の上で遊ぶと土壌菌をはじめとした様々な菌を手に入れることができます。
そして、遊びで体を動かすことによって腸に刺激を与えてもくれます。
また、色々なにおい、音、風景、感触を経験することによって五感が発達し、脳にもよい刺激を与えます。
脳腸相関ということがあります。脳と腸は常にお互い連絡を取り合っています。脳が良いことは腸にもよい影響を与えるのではないかと思います😊
たくさん笑いましょう。

腸には免疫細胞の70%が存在しますが、その代表的なものはNK細胞という細胞です。
このNK細胞は「笑い」によって活性化されるという研究結果がでています。
「笑い」によって、免疫が上がるということですね。また、「笑う」ことによって、リラックスし副交感神経が優位な状態になることで腸の働きがよくなることもあります。
この「笑い」はゲラゲラ笑わなくても、口角を上げるだけでも効果があるみたいですよ。
大人の私たちもいつも笑顔を。心がけるといいですね😅😅
まとめ
細菌=悪いもの、汚いものという印象がありますが、私たちの体はたくさんの細菌があらゆす仕事をして支えられています。
悪玉菌の大腸菌でさえも、有害物質を産生を抑えてくれたり、ビタミンB₂、B₆を作るなどの働きをしてくれています。
体の中で善玉菌、悪玉菌、日和見菌すべてなくてはならないものです。
ほんと社会の構図に似ていますね。
どれだけ、その細菌たちが住みやすく、節度を守って暮らしていってくれるか。私たち大人は子どもは体を守っていくうえで、それらの細菌たちも一緒に育てていく気持ちで生活していくべきですね。
子どもの腸活は、たくさんの人、自然にふれてたくさんの種類の細菌を獲得し、細菌たちのエサとなる食べ物を食べ、たくさん寝て、たくさん遊び、たくさん笑おう。
まだまだ暑い日が続き、なかなか環境的に外でおもいっきり遊べる状況ではないですが、秋になって気候がよくなってきたら、おいしい秋の食物を食べながら外でたくさん子どもたちと遊びたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも役にたつ内容があればうれしいです。
参考:子どもの幸せは腸が7割 監修藤田紘一郎 西東社
面白くて眠れなくなるウンチ学 佐巻健男 PHP