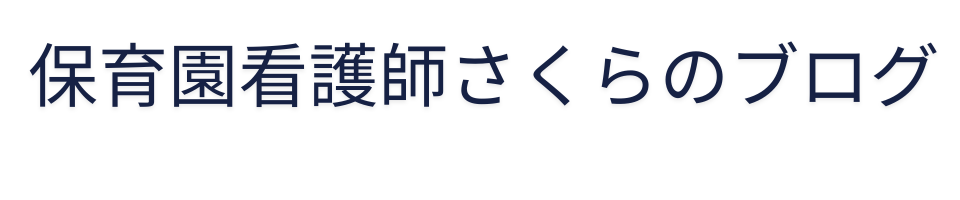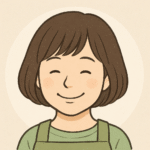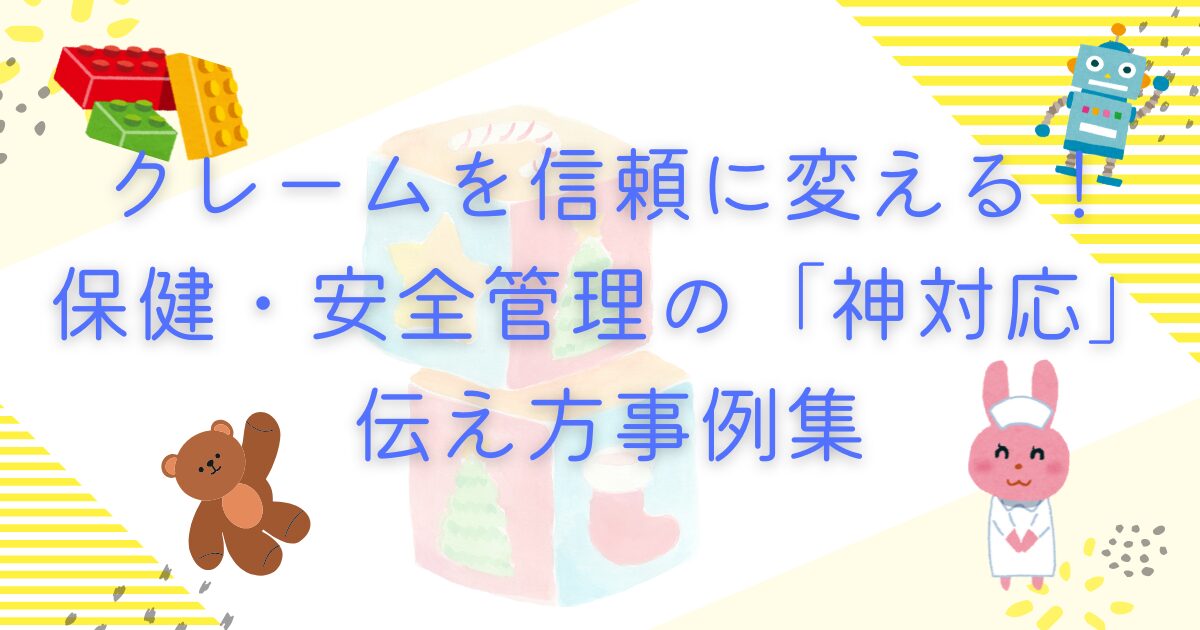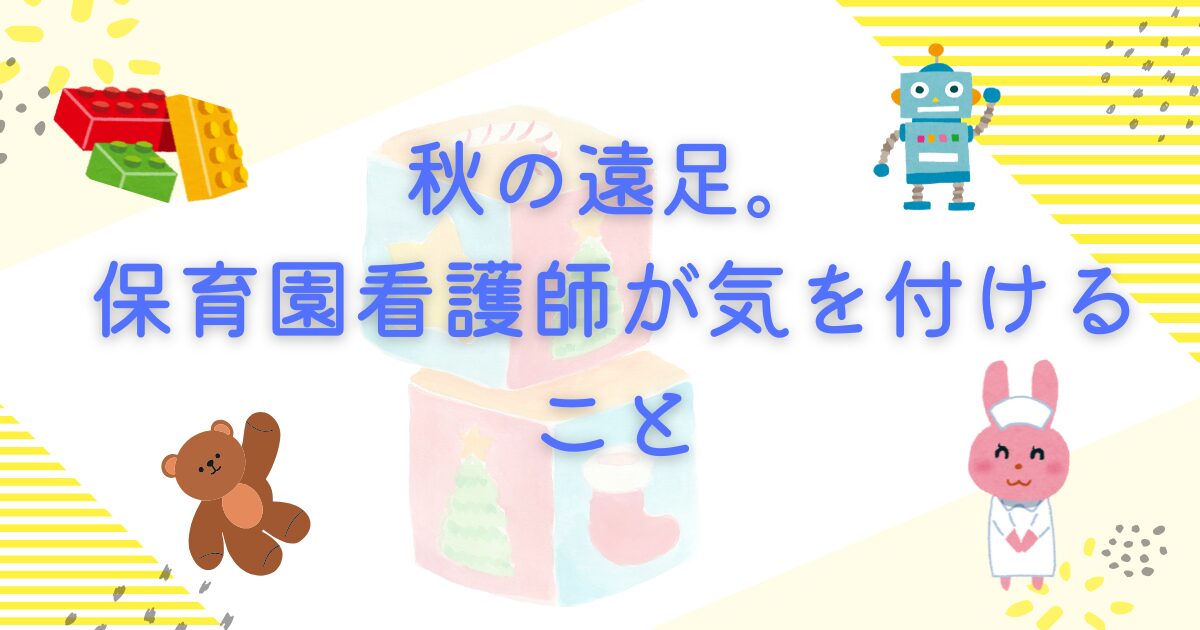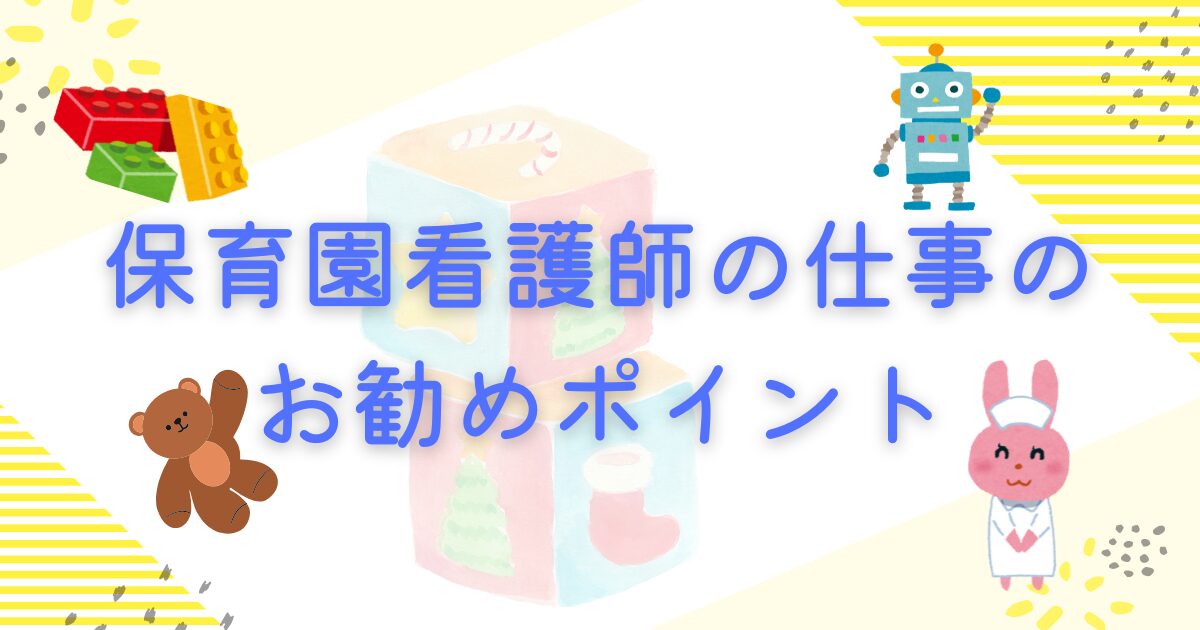保育園看護師が解説!症状別ケアの実践録(1)
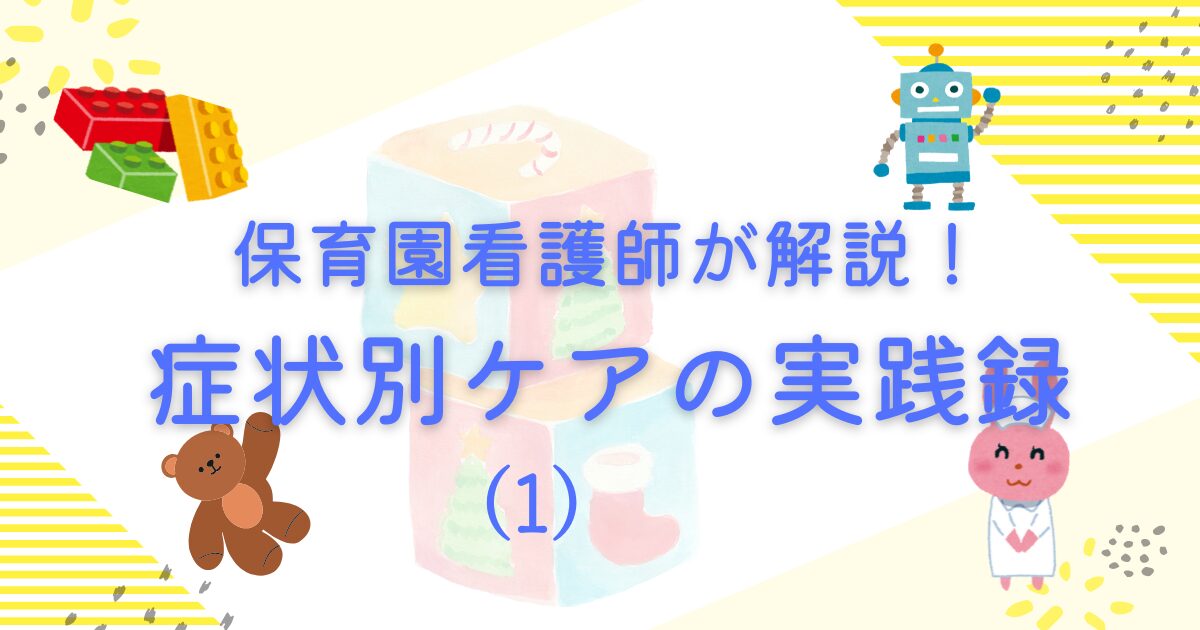
こんにちは。保育園看護師さくらのブログをご覧いただきありがとうございます。
このブログでは、保育園看護師のお仕事について、また子どもの病気のことなど子どもに関わる方に向けてお話させていただきたいと思っております。
今回は子どもからの訴えが多い「頭痛」「腹痛」よくある症状「機嫌が悪い」という症状について、私が日頃どのようにケアをしているのか載せてみたいと思います。
参考になればうれしいです。
頭痛
「頭が痛い」とはっきり言えるのは大きい年齢の子になってしまいますが、小さい子も機嫌が悪かったり、元気がない場合は。
まず、検温をします。
発熱がある場合

発熱がある場合は、理由があるので解決します。お迎えをお願いすることになります。
ただ、発熱があった場合は、軽い熱中症や脱水の症状かもしれないので、涼しい場所に移動して水分を飲んで少し休むと熱がスーッと引いて元気になる場合もあるので、その場合は保護者に連絡し園で過ごすこともあります。
発熱がない場合

この時も、もしかしたらこの後、発熱するかもしれないため、水分補給をしてベットで休ませて様子をみます。
顔色が悪かったり、元気がなかったりするときは、水平の姿勢でタオルなどで足を高くして寝かせます。
この時、食欲や睡眠状況、病気などしてなかったのか等本人や連絡帳、担任、保護者などから情報を得ます。
改善しない場合はお迎えを依頼します。
片頭痛
大きいクラスになると、片頭痛持ちのお子さんも増えていきます。お父さんお母さんがそうだったりすることも多いですね😔
血管が拡張して神経を刺激するため頭痛を引き起こすようです。
症状:ズキンズキンと波打つような強い痛み。嘔吐や悪心などが生じる場合があり、光や音、匂いに対して過敏になることがあります。
園での対処法:体を動かすことで悪化することがあるため、暗くした部屋で横になって休ませる。頭を冷たいタオルなどで冷やしてあげる。
緊張性頭痛
首や肩の筋肉の緊張による血流の悪化が考えれます。
症状:頭全体が締め付けられるような痛み。肩こりを伴うこともある。
園での対処法:首や肩のあたりを温め、血行をよくしたり、マッサージをしたりする。
片頭痛と緊張性頭痛の混合型
片頭痛、緊張性頭痛の両方の症状がある場合は、頭を冷やすで良いようです。
ただ、子どもが嫌がるようならない何もせず、静かに過ごしたり、横になったり、リラックスできるように環境を整えてあげればいいのかなと思います。
ただ、いずれにしても、頭が痛くて辛そうな場合は、お迎えをお願いし受診や内服薬などで早く頭痛の症状を楽にしてあげたいですね。
頭をぶつけた場合
ぶつけた部分を冷やして様子をみても痛みが治まらない時は受診もしくは救急車搬送します。
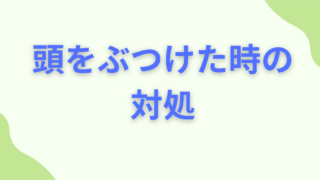
腹痛

排便が原因の場合
子どもの腹痛の8割は「便秘」ではないかと自論ですが思います。
大体、うんちがでていない。またはしたい。が多いのかなと。
なので、「お腹が痛い」と訴えがあった場合は、とにかくうんち情報を集めます。連絡帳であったり、子どもの情報だったり、
「うんちに行きたい?」と聞いて「うん」と答える子はトイレに直行!
なかなかでない場合は、お腹をさすってあげたり、少し温めたりするとスルっとでて解決する場合があります。
次は「胃腸炎」の場合、下痢でお腹が痛い場合、これも本人や連絡帳などで情報を得て、お迎えを依頼したりします。食中毒なども念頭において、下痢がでたら便の状態を観察し、写真を撮ったりして保護者にもお伝えします。
排便以外の原因の場合
排便をしても治らない、もしくはいつもと同じように便がでている。
検温をする。
心理的なものが疑われる場合
発熱がなく、顔色も良く、比較的元気な場合
すこし休ませて、お腹を温めたりして様子を見ます。少したわいもない話をすると「大丈夫」と笑顔になって治る場合もある。
虫垂炎の疑いがある場合
発熱がある場合もある。また、嘔気や嘔吐が伴ったり、動くと痛みが増強することがあります。お迎え状況や痛みが強い場合は救急車要請も考えます。
腸重積、腸閉塞、鼠径ヘルニア嵌頓、精巣捻転の疑いがある場合
腸重積は激しい痛みが強まったり治まったりを繰り返すことがあります。またイチゴゼリーのような便が出る場合も。
腸閉塞、鼠経ヘルニア嵌頓、精巣捻転は鼠径部や陰部、陰嚢に発赤や腫れが伴っていないか?
これらの病気が疑われる場合はすぐに救急車要請します。
デリケートゾーンのため、特にプライバシーに注意し、観察する必要があります。
IgA血管炎(アレルギー性紫斑病)の疑いがある場合
腹痛と特に足や腕、お尻に赤紫色の発疹がみられることがあります。
発疹は定規などの透明なものでおさえても、色が変わらないのが特徴です。
お迎え状況や腹痛が強い場合は救急車要請も考えます。
お腹をぶつけた場合
お腹の痛みが続く、嘔気や嘔吐があったり、皮膚の色の変化などあった場合は至急、受診や救急車要請をします。
機嫌が悪い

特に、0歳、1歳の小さいお子さんですよね。
自分で「痛い」「眠い」「おなかすいた」「苦しい」など表現できない場合。
熱はない
顔色も悪くない
目は赤くない、めやにが出ていない
むくんでいない
どこも赤くない、腫れもない
鼻水もない、咳もない、ぜこぜこもしていない
見た感じ悪いところはなさそうだけど、
なんかグズグズ調子が悪そう??
抱っこしても、あやしても、遊ぶこともできない。
そんな時は耳(中耳炎?)かもしれません。または排泄の問題?何かの病気の前兆?
ただ、いつもと違う。遊ぶことができない。なんていう場合は保護者に報告して家での様子を教えてもらったりします。
そして、お給食が食べれないようならお迎えをお願いします。
たまーに「家に帰ってもなんでもなかったです🥵」と少しお怒りモードの保護者の方もいますが、
なんでもなかったら、それで良し!なんかあってからじゃ困りますからね😓
最後に。痛みは病気からではないかなと疑いがある子には。
たまーに、プラシーボ効果を使います。
小さいカップに水を入れて、「この薬はとっても良く効く薬だよ」と言って飲ませます。
そうすると、大抵の子は飲み終わると「痛くなくなった!」と笑顔になります😅
また、頭痛の時は冷たいタオルで冷やしてあげたり、腹痛の時は暖かいタオルで温めたり、それ自体も痛みを緩和させてくれる効果がありますが、子どもも何かしてもらったというのがうれしいようで、満足して帰っていくことが多いです😊かわいいですね😍
まとめ
子どもが「頭、痛い」「お腹、痛い」と訴えてきた場合、まず、「痛いんだね、教えてくれてありがとう」と伝えます。
そして、それが救急な病気ではないか。少し休めば治るものなのか。それとも排便や看護ケアでよくなるものなのか。判断します。それは、子どもの体調や食事や睡眠状況や周りの感染症状況、既往歴、精神的なもの。様々のことを考えて判断しなくてはなりません。
ただ、甘えたかった場合も多々あります。そういう時は、「つらかったね。痛かったんだね」と伝えるだけでも子どもは満足して元気になったりします。
保育園にいる間は「私たち」が全責任を負います。「大丈夫」と思わないで、最悪を意識しながら保育に携わらないといけないなと痛感しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。少しでも参考なる内容があったらうれしいです。