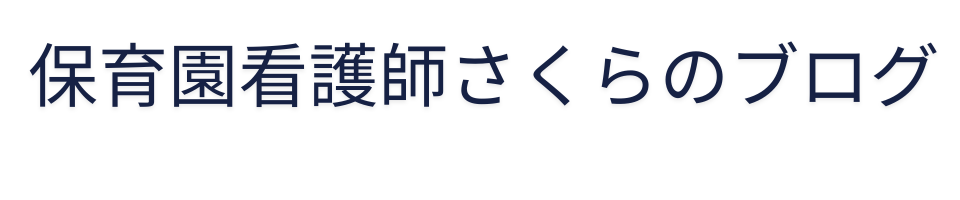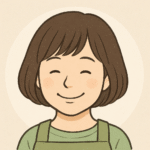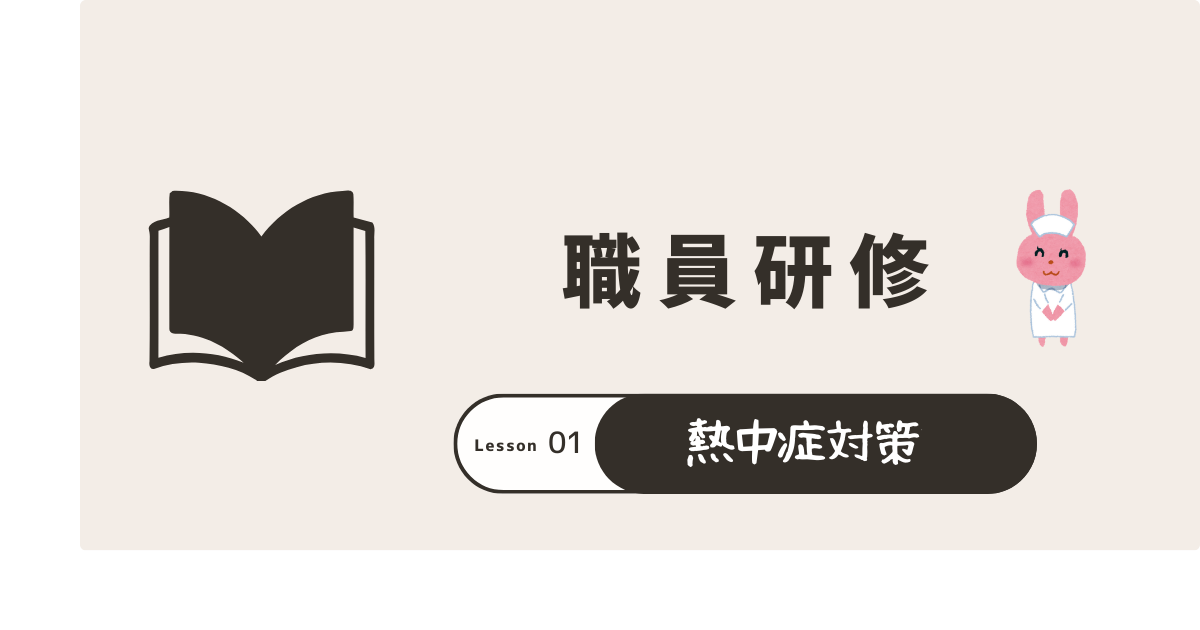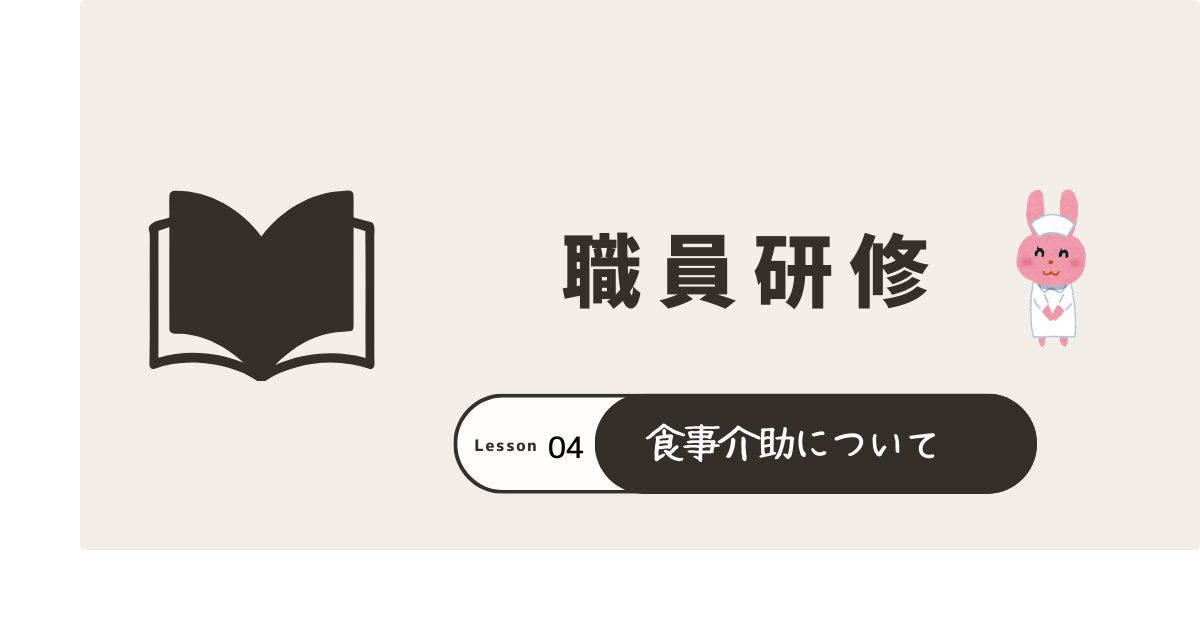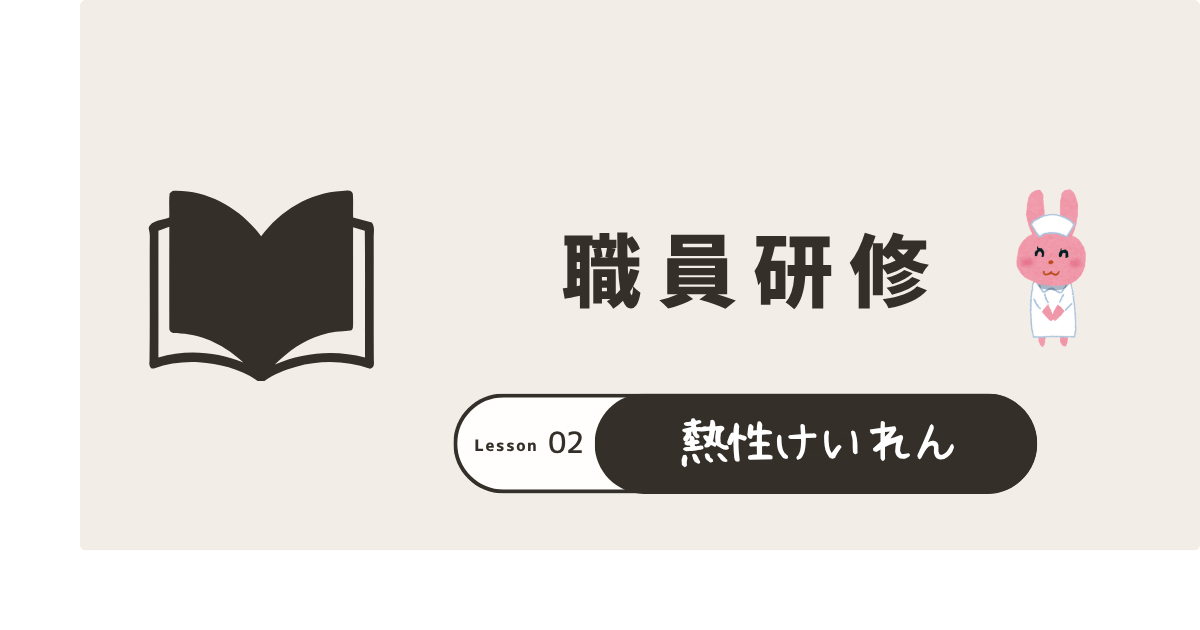職員園内研修 心肺蘇生、人工呼吸 (CPR)
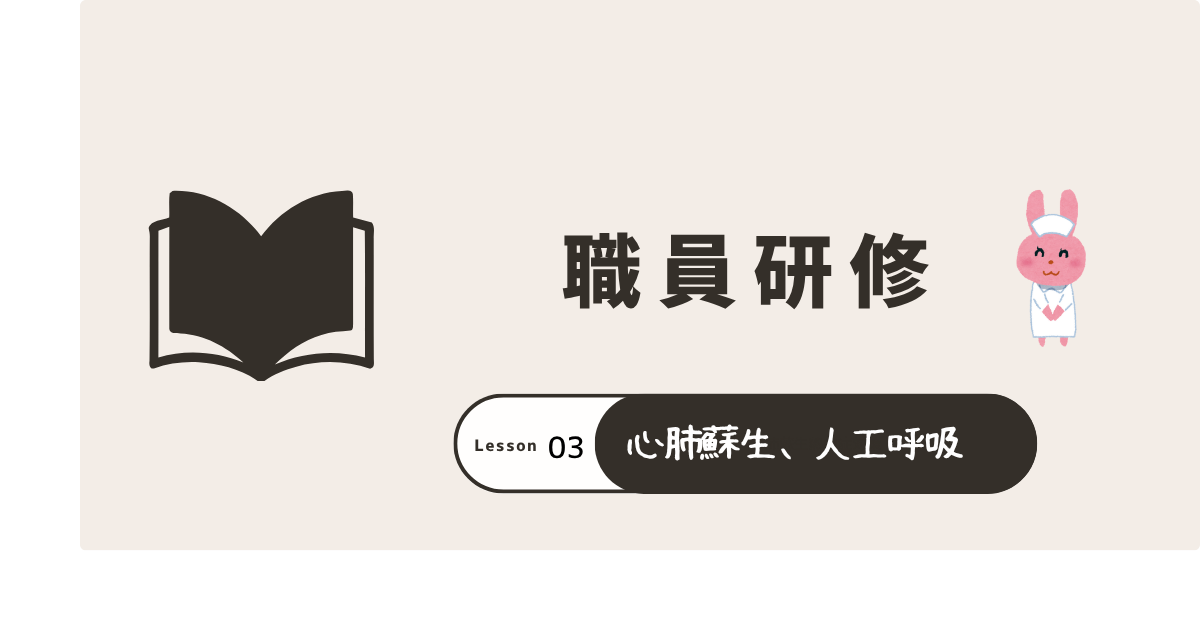
こんにちは。保育園看護師さくらのブログをご覧いただきありがとうございます。
このブログでは、保育園看護師のお仕事について、また子どもの病気のことなど子どもに関わる方に向けてお話させていただきたいと思っております。
園ではこの研修は看護師が担当することが多いですよね。
ただ私みたいに、臨床から年十年も離れている看護師からしては、私なんかから教わるより消防署で教えてもらった方が絶対有益でしょう!と思うのですが😓😓
できるのであれば、消防士さんに来園していただきお願いするのが一番かと。
でもそういうことができない場合のためのいつも私がやらせていただいている研修を紹介したいと思います。
手技に関しては、保育士の先生たちも色々な所で研修をしていて、頭の中ではわかっているという先生も多いですが、あまりわからないという先生もいるので、基本にのっとりながら、また、「こういうこともあるんだよ」「いざとなったら、どうだったかなという疑問もでてくるかな」など思い、想像しながら研修内容を考えてみました。
ASUKAモデル
どういう時に心肺蘇生をするか、迷うことがあると思うんですね。
意識がない、呼吸がない。明確にわかればいいのですが、
「これは、呼吸しているのか」「わからない時はとりあえず心肺蘇生しなさいと言われているが」「どっちなんだろう?不安」「10秒間で判断しないと💦」
きっと、人間だから「大丈夫」な方を思いたい!というようになると思います。
でもこの動画をみれば、こういうこともあるのか!と知識として認識できると思います。
ほんとに有益な動画なのでぜひ、見てもらいたいです。
ASUKAモデルhttps://www.youtube.com/watch?v=Eo_kx_ZyRik
今から14年ほど前、さいたま市で駅伝の練習中に小学6年生の児童が亡くなった話です。
何度見ても、身が引き締まり、このようなことがないようにしっかり保育していかなければと再認識する動画です。
子どもに関わっている重大な仕事している責任を苦しくなるくらい感じます!
「死戦期呼吸」という、死の前に起こる 口を開けあえぐような呼吸
この呼吸が先生たちは「呼吸している」と判断してしまい、胸骨圧迫、AEDと使用しなかった。
「こういうこともある」と知っているのと知らないのでは対処が全然違いますよね。
「規則的な呼吸をしているかしていないか」が心肺蘇生をする判断になるということ!
心肺蘇生 AED

心肺蘇生、人工呼吸の実演は消防署などから心肺蘇生用のお人形をお借りできればそれを用いるのがベストですが、とりあえずの場合は園にあるお人形で行うでもよいと思います。
(小児、大人の場合でも)
- 周囲の安全確認:周囲の状況を見まわし、自分自身が近づいてもケガをしないことを確認する。
- 全身の観察:傷病者に近づきながら、出血などないか確認する。
- 反応の確認:軽く肩や足の裏を叩きながら、耳元で声をかける。
- 応援の要請:反応がなかったら、「誰か来てください」と助けを求めて119番通報とAEDを持ってきてもらうよう要請する。保護者にも連絡する。園児情報の書類を準備しておく。またその時子どもが周りにいる場合は他の職員が別の場所に誘導する。
- 呼吸の確認:胸やお腹を見ながら普段通りの呼吸があるかどうか確認する。(10秒で確認)普段通りの呼吸がない、もしくはわからない場合は直ちに胸骨圧迫を開始する。
- 胸骨圧迫 1分間に100~120回のテンポで絶え間なく行う。(♪もしもしかめよ。♪アンパンマンマーチなどのテンポ)大人:5cm沈む程度。子ども:胸の厚さの3分の1沈む程度。
- 人工呼吸 顎を上に向かせて気道を確保して、倒れている人の鼻をつまみ2回人工呼吸する。人工呼吸用のマウスシートを常に各部屋に常備しておくことも大切ですね。
- 胸骨圧迫30回 人工呼吸2回のサイクルをAEDが到着するまで行う。
- AEDを使用する。 AEDの電源を入れたら音声ガイダンスの説明に従う。どの機種も基本的には「電極パットを貼る⇒電気ショックのボタンを押す」・電気ショックが必要がどうかはAEDが心電図を解析して、電気ショックが必要な時だけ電流が流れます。AEDは物によって微妙に違う場合もあるため、実際、園のAEDで試してみたり、AEDの説明動画がYouTubeにあがっていたら、それも含めて見るのもよいですね。
- ショックが終わったら、「胸骨圧迫30回、人工呼吸2回」を再開する。(パットは貼ったままで)2分後再びAEDが心電図の解析を始めます。「体から離れてください」とガイダンスが流れたら指示に従う。救急隊が到着するまで絶え間なく続ける。
電極パットを貼るときの注意点
・汗や水分は拭いてから貼る ・湿布や医薬品を貼っていたら剥がして貼る
・アクセサリーは電極パットの下にならないようにずらす
・ペースメーカーは3センチ以上離して貼る
・ブラジャーははずす必要はないが、金具が電極パットに触れないようにする
※AEDを使用して回復した場合でも救急隊に引き渡すまで電極パットを装着し電源もONにしておく。
※園の職員をCPRする場合は胸がさらされないようにハンカチで覆うなど特に配慮が必要ですね。
各時間帯による訓練

園では早番の時間、通常の時間、遅番の時間、土曜日保育、園外保育など時間帯によって職員の人数が変わりますよね。
その時間に合わせたシュミレーションも必要だと思います。
特に早番、遅番の時間帯は職員が極端に少なくなるのと同時に受け入れや引き渡しもあり、具合の悪い園児がでたら大パニックになりそうです。
2人体制の園だとしたら、1人は対象園児のつく。もう1人の職員がすべてに対応しなくてはなりません。救急車要請、保護者連絡、園児情報書類、AED、他の園児の誘導など。そしてお迎え、引き渡し。
なので、電話やAEDは部屋に置くまたはすぐ近くに置く。園の住所や電話番号が書いてあるメモを電話に貼っておく。書類はすぐだせるようまとめて置いておくなど。その園独自のマニュアルをその場で職員同士で話し合って決める場にするのもいいですね。
まとめ
心肺蘇生人工呼吸については園の職員の中でも知識がある人とない人の差がかなりあると感じています。
なので、こんなことわかっているだろうから伝えなくても大丈夫という気持ちはなしに基本に忠実に行っています。
「意識がない」「息をしているかよくわからない」の場合はまず胸骨圧迫!
まったく必要でなければ、顔をしかめたり、手ではらいのけたりするはず。
心肺蘇生をする行為はとっても勇気がいること。また慣れもあると思います。
小さな研修を1年に1度ではなく、1年に3回くらい行うと体もスムーズに動けるのではないかと思います。
少しでも参考になればうれしいです。