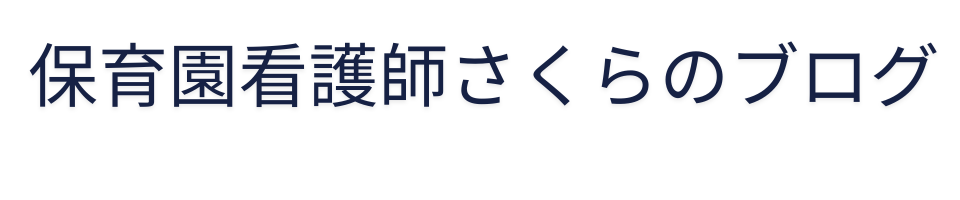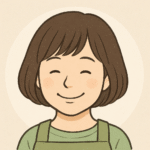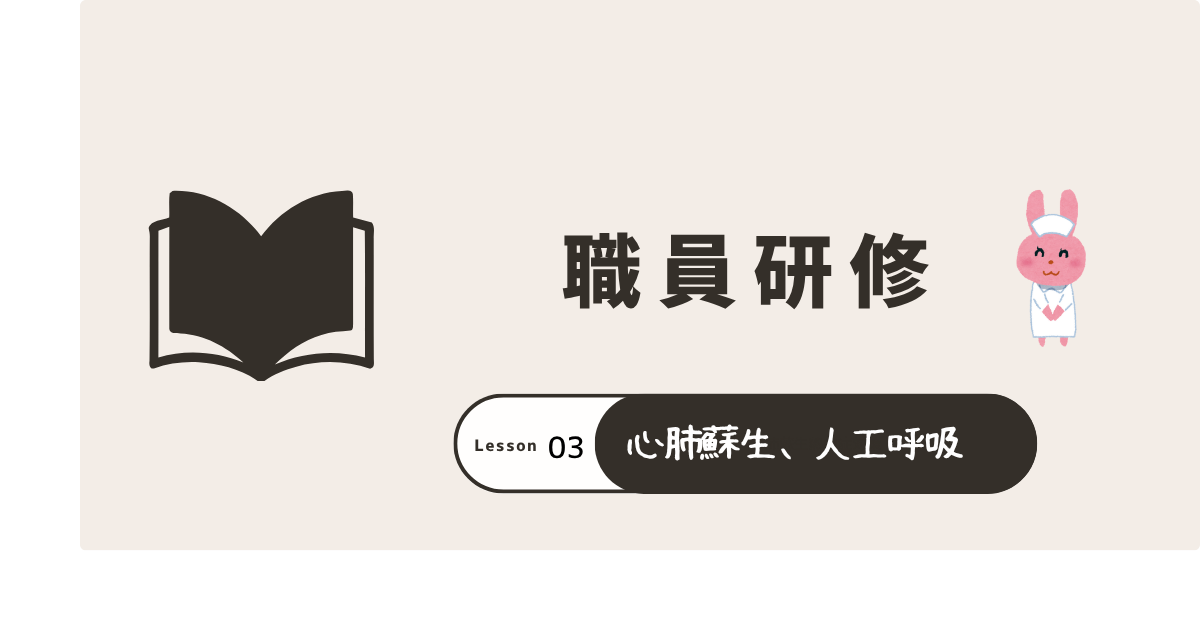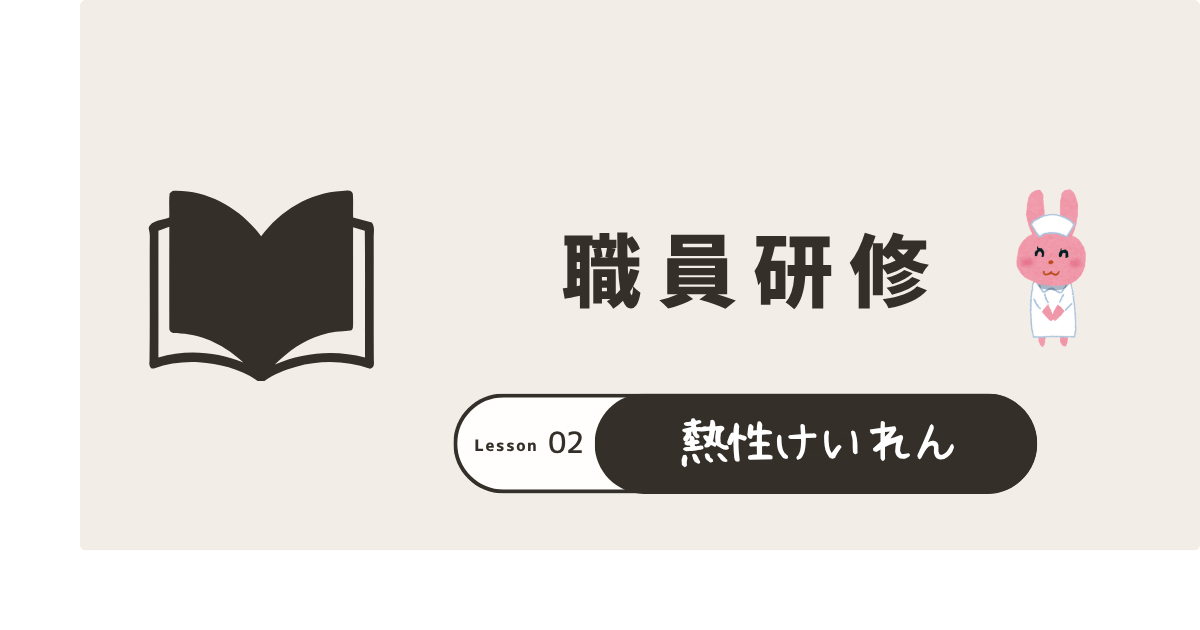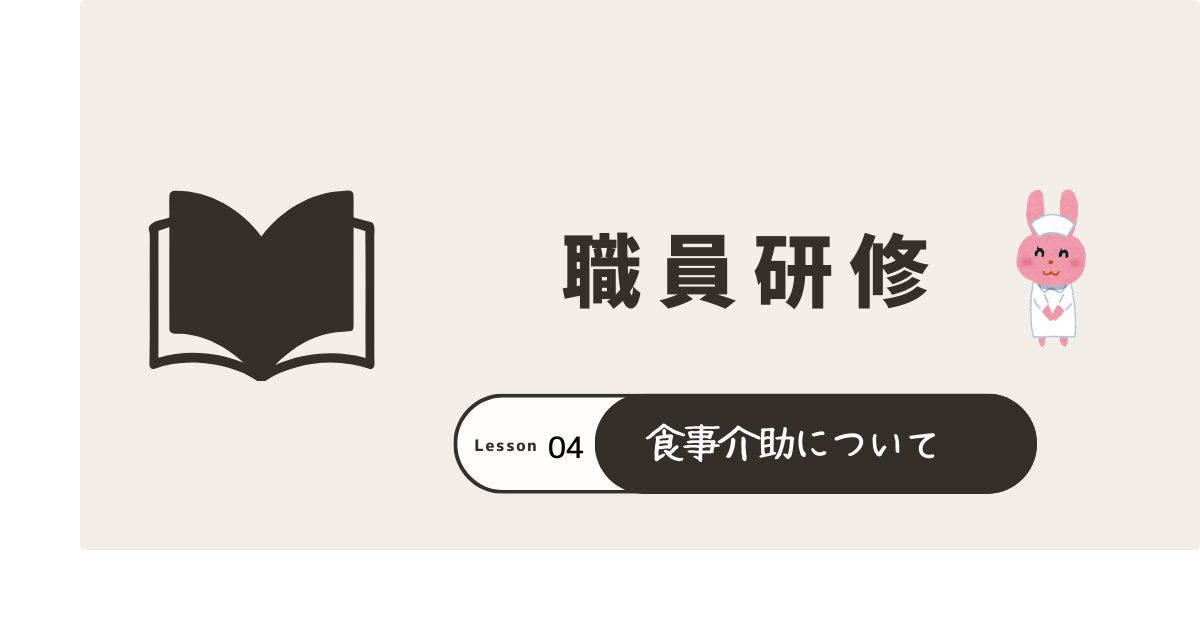職員園内研修(熱中症対策)
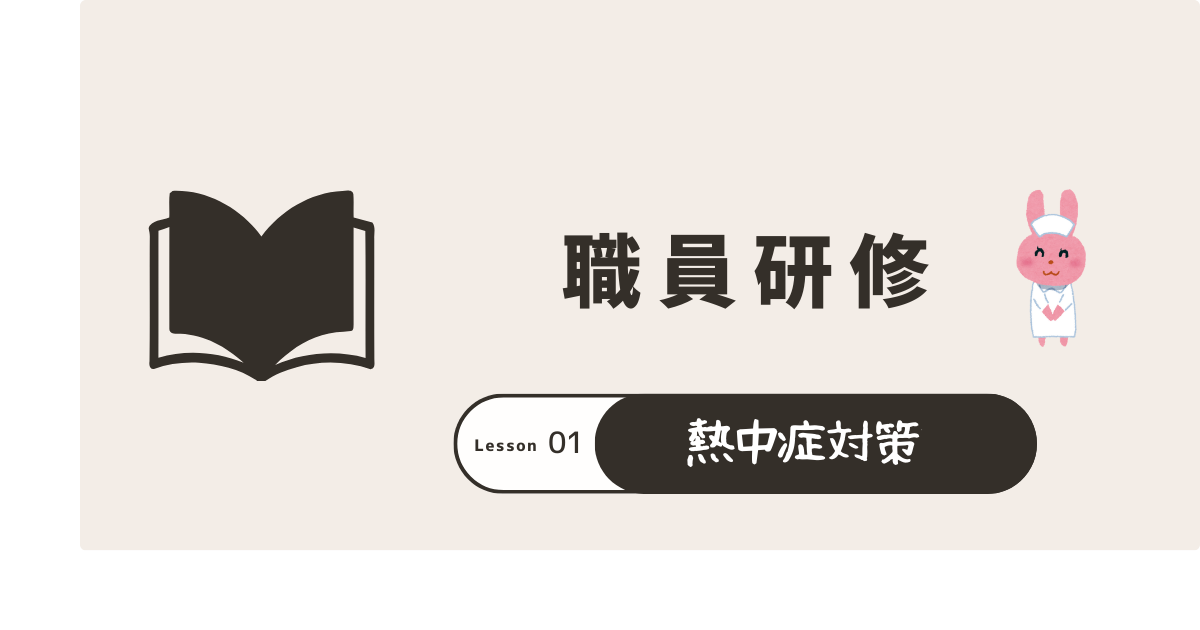
こんにちは。保育園看護師さくらのブログをご覧いただきありがとうございます。
このブログでは、保育園看護師のお仕事について、また子どもの病気のことなど子どもに関わる方に向けてお話させていただきたいと思っております。
6月に入ると私の園では、熱中症対策について園内で全職員にむけて研修を行います。
先生たちも「熱中症」についてはたくさんの知識と経験を持って対策してくださっていますので、新しく就職された先生にこの園の対策を伝える。また先生たちと対策を再確認しあうといった研修になります。
熱中症とは
体温を平熱に保つために汗をかき、体内の水分や塩分(ナトリウムなど)の減少や血液の流れが滞るなどして、体温の上昇して重要な臓器が高温にさらされたりすることにより発生する障害の総称。高温環境下に長時間いたとき、あるいはいた時の体調不良はすべて熱中症の可能性がある。(環境省:熱中症環境保健マニュアル2018)
むずかしい言葉ですねー。
とにかく高温の環境にいて、体の調子が悪くなった場合はすべて熱中症の可能性があるということですね。
そしてとても怖く、命にかかわるのであるけれど、予防法を知り実践すれば完全に防ぐことができるということもこのマニュアルでは記しています。
「熱中症から子どもを守る」
私たちの手にかかっているということですね!
熱中症になりやすい時期
梅雨の合間の急激に暑くなった時期
まだ、体が暑さに慣れていない時期ですね。「暑熱順化」ができていない時期は体も油断していますからもっとも危険な時期です。
梅雨明けから8月いっぱい
本格的な夏。今年も暑そうですね🌞
たぶん、10月ごろまでは油断できないですかね?
熱中症になりやすい要因
①環境
高温、多湿、風が弱い、輻射源(熱を発生するもの⇒照り返しなど)
厚労省のマニュアルでは、保育室の室温は夏は26~28℃ 湿度は60%となっています。
また、直射日光が入らないように、カーテンやすだれなどで対策することも必要ですね。
②体
高齢者、乳幼児、肥満、持病がある、低栄養状態、脱水気味、体調不良、暑さになれていない。
なぜ、乳幼児は熱中症になりやすいのか?
・体温調整機能が未熟なため、汗をかいて体外に熱を放散する力が未発達。
・大人より地面からの照り返しの影響を受けやすい。
・遊びに夢中になって、身体の異変に気付きにくい、また訴えることが難しい。
体調が悪いときも熱中症の引き金になる
寝不足、食欲不振、下痢、嘔吐、機嫌が悪いなど。
・暑くて前夜あまり眠れていない。
・朝、食欲がなくあまり食べられなかった。
・朝、軟便だった。
脱水状態であったり、もともと体調が悪い上に暑い環境に入ったら想像しただけでもしんどいですね( ;∀;)
③行動
激しい運動、慣れない運動、長時間屋外にいる、水分補給がしにくい。
暑さ指数27℃以下で外遊びをしても、子どもの顔色や汗の状態などを把握しながら、無理のない時間できりあげるのも大切ですね。水分補給は30分毎に飲水するように促すのも大切ですね。
早く遊びたいがために、「飲んだよー」と飲む真似をする子もいますので、水筒の中身を確認することも必要かもですね(苦笑い)
暑い環境下になったとき、どのように私たちの体は熱を下げているのか?
そもそも、私たちは自分の力で熱中症にならないように、熱を外に放散する能力がそなわっています。どのようにしているのでしょうか?
末端の血管を拡張させて熱を放散する
①気温の上昇などで体内が熱くなると、体内の熱を血液に移す。
②熱い血液は皮膚の表面に行く。
③血管を拡張させて血液を冷やす⇒外気温で冷やします。手足の末端や頬っぺたが赤くなったり、熱くなるのは血管が拡張して血液が集まってくるからなんですね。
④血液が冷えたら体に帰っていく。
また、
汗をかいて体の熱を下げる
発汗することで気化熱を利用して体温を下げます。
※気化熱は「打ち水効果」といって、皮膚の上の汗が暑さで蒸発するときに一緒に熱も奪ってくれるというもの。
皮膚にじわっとかくような汗は蒸発したときに熱を下げてくれますが、反対にぽたぽた流れるような汗は蒸発しないので無駄な汗となり、蒸発しないため体温が下がらない。そのため体はどんどん汗をかいて体温を下げようとするため脱水が進みます。
⇒結果、体の中の臓器の血液量が減る。全身に影響がでる!
・頭に血液量が減ると、めまいや頭痛を。ひどくなると意識障害など。
・胃腸の血液量が減ると、嘔吐や胃痛、気持ち悪さなど。
全身にさまざまな症状が出現します。
ですので、子どもの頬っぺたが赤くなったり、じんわり汗をかいてきたら、熱中症を念頭において環境を見直したり、注意深く様子をみていく必要がありますね。
熱中症の症状による重症度と対処法
熱中症の症状と重症度分類


熱中症時の冷却方法
・首筋、わきの下、鼠径部などの太い血管が通っている部位に保冷剤をタオルに包み冷やす。
・水に浸したタオルを体に広くのせ、うちわで仰ぐ。
※散歩などで具合が悪くなった場合は、自販機やコンビニで冷えたペットボトルを購入し、上記部位にあて冷やすというケースもあるかもですね。お散歩バックに小銭は常備ですね。
水分補給
・冷たい飲み物がベスト(5~15℃くらい)
・経口補水液がベスト ★手作り補水液(水1ℓに塩3g、砂糖40g)
熱中症を防ぐポイント
・子どもの顔色や汗のかき方を十分に観察する
それに加えて、活気があるか、笑顔があるか、食欲があるか、睡眠はとれているか、または寝すぎていないか、熱はないかなど普段とちがう様子があった場合も十分観察し様子をみます。
・適切に飲水させる
カフェインが入ってなくミネラル豊富な麦茶がベスト!
30分に1回は水分補給の時間をとる。
・服装は適切か
吸湿・速乾のぴったりの下着に上着(Tシャツ類)は空気が入りやすいゆったりしたもの「煙突効果」が期待できるものがベスト。
吸湿速乾性のある下着かパっと気化熱を利用して体温を下げてくれる効果とゆったりとした上着は下着と上着の間に空気が流れて一層涼しく感じられる服装です。
・子ども個人の体調を考慮する
体調、食事状況、水分摂取状況、睡眠状況、基礎疾患など。
特にいつもと違う様子がある場合は、外遊びには参加せず、室内で遊ぶよう対策をとる。
職員の人数的に厳しい場合もあると思いますが、合同保育などこの季節は必要かもしれませんね。
・暑さ指数28℃以上は外遊びを禁止する
気温35℃(湿度50%以下の場合)までしか人は生存できないと言われています。また輻射熱を考えると、子どもの位置ではさらに2℃上がると言われています。
暑さ指数は子どもの高さで測ることが大切です。
28℃を超えたら、速やかに園に帰ってくる。園舎にはいる。
・体を暑さに慣らす
本格的に暑くなる前に軽い運動をして汗をかく練習をする。(暑熱順化)
運動直後30分以内に糖質とたんぱく質を含んだ食品(牛乳など)を補給することで血液量が増加し、熱放散能力が改善すると言われています。しかし体に良い牛乳でも飲みすぎはよくありません。適量を守ってしっかり飲むことが大切です。
以上、研修の内容です。
熱中症について レジュメ
参考: 日本救急医学学会 熱中症診療ガイドライン2015
環境省 熱中症環境保健マニュアル2018
厚労省 保育園における感染症対策ガイドライン2018